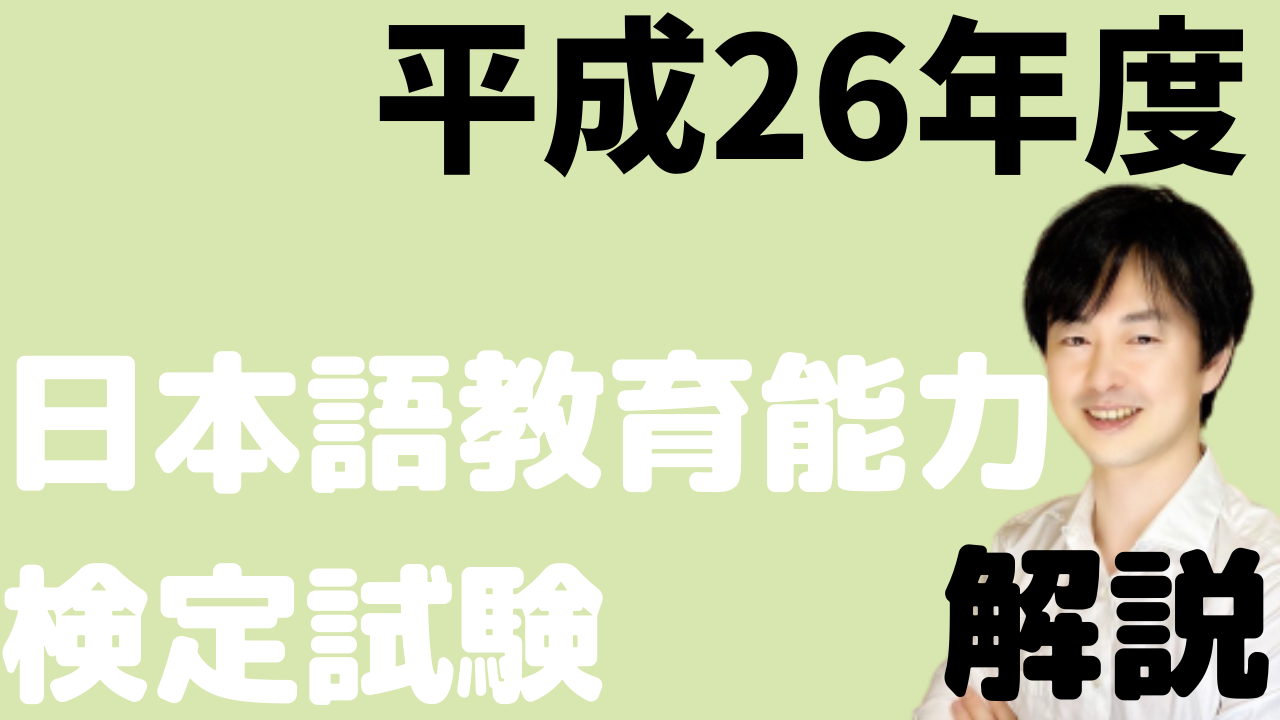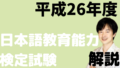新解説
(14)
ポイントは「指示する対象語との関係」です。
1と3で迷った人が多いのでこの2つを検討します。
ますは3「現場指示」と「文脈指示」
現場指示「ねこがいます。あそこにいます」
文脈指示「昨日、猫カフェというお店にいきました。そこは猫の楽園でした」
上の通り「現場指示」と「文脈指示」の違いは
「現場に実際にあるものを指すのか」「談話に出てきたものを指すのか」という違い。
「指示する対象語」は関係ありません。
次に1「前方照応」と「後方照応」
照応とは、代名詞(彼、彼女…)や指示詞(これ、それ…)を使って、他の物を指すこと。
例)私は今日、Aさんとデートの約束をしていたが、彼女は現れなかった。
上の文章の「彼女」は、「Aさん」を指しています。これが照応です。
前方照応とは、対象語が前方にある照応
前方照応の例)アインシュタインは学校の成績はまるでだめだった。これは有名な話だ(現代日本語文法⑦p30より)
後方照応とは、対象語が後方にある照応
後方照応の例)これは有名な話だが、アインシュタインは学校の成績はまるでだめだった(現代日本語文法⑦p31より)
上記のとおり、「前方照応と後方照応」は「指示する対象語」との関係で分けられます。
(15)
下線部の前の「談話のまとまりをもたらすもの」は何かという観点から各選択肢を検討します。
選択肢1 ×
Yの「それ」という代名詞が、Xの「熱があるんです」を指すことで、談話がまとまっています。
言語的要素によって談話のまとまりをもたらしています。
選択肢2 ○
Xの「(私は)おなかがすいた」とYの「台所にカレーがあるよ」という2つの文章は、主語も異なっており、言語的なつながりはありません。ですが、YはXの「おなかがすいた」という発言から、「何か食べ物が欲しいんだろう」と推論して「台所にカレーがあるよ」と答えています。
発話内の言語的要素ではなく、推論によって談話がまとまっています。
選択肢3 ×
X「渋谷へ行こう」Y「(渋谷は)混んでいるよ」
Yでは省略された「渋谷」という言語的要素によって談話がまとまっています。
選択肢4 ○
X「クマのぬいぐるみが欲しいな」Y「(クマのぬいぐるみは)お子さんへのプレゼントですね」
Yでは省略された「クマのぬいぐるみ」という言語的要素によって談話がまとまっています。
YはXがクマのぬいぐるみが欲しい理由を推論しているので、推論によって談話がまとまっていると言えるかもしれませんが、「クマのぬいぐるみ」という言語的要素も談話のまとまりをもたらしているのは間違いありません。「クマのぬいぐるみ」という言語的要素が共通しているのは明らかなので。
つまり、「言語的要素ではなく」と言い切れません。
「言語的要素と推論によって」談話がまとまっていると思料します。
旧解説
平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰの問題3のCは【文章のまとまり】です。
(11)
「とても軽くて、よく飛んだ」と言われたら、「何が?」となります。つまり、動作の主体、主語が省略されています。
よって、正解は3です。
(12)
文と文を関連づける仕組みを結束性といいます。
よって、正解は1です。
(13)
1,一文目は「彼女」のことを述べていないので、文が繋がっていません。
2,一文目は「彼女」のことを述べていないので、文が繋がっていません。
3,一文目は「彼」のことを述べている(友達)ので、文が繋がっており、代名詞「彼」が文と文の関係を表すのに使われています。
4, 一文目は「彼」のことを述べていないので、文が繋がっていません。
よって、正解は3です。
(14)
内の関係と外の関係については、平成27年度 日本語教育能力検定試験Ⅲの解説 問題3を参照。
現場指示と文脈指示については、平成23年度 日本語教育能力検定試験Ⅰの解説 問題1の(8)を参照。
・前方照応は、前を照らします。
例…僕は猫を買っている。彼女はササミが大好物だ(「彼女」が前方の「猫」を照らしている)。
・後方照応は、後ろを照らします。
例…僕が新しく買ったスマホはこれ。iPhone7です(「これ」が後方の「iPhone7」を照らしている)。
(平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(8)【指示詞の現場指示・文脈指示用法】の2も後方照応の具体例になります。)
以上より、正解は1です。
(15) 発話内の言語的要素ではなく、推論が談話のまとまりをもたらすものを選ぶ問題です。
1,Xの「熱」を、Yの「それ」が受けているので、言語的要素が談話にまとまりをもたらしています。
2,X「おなかすいた」
Y「台所にカレーがあるよ」
という2つの文には言語的要素では、談話にまとまりをもたらしていません。
まとまりがある、と思う人は、すでに推論しています。
例えば、
X「(私は)おなかすいた」Y「(あなたは)晩御飯食べてないの?」とか
X「食べ物何かある?」Y「(食べ物は)台所にカレーがあるよ」であれば、
省略された主語という言語的要素によって談話にまとまりをもたらしています。
一方、
「おなかがすいた」と「台所にカレーがある」は主語も異なり言語的要素だけを見ればまとまりがないです。
しかし、普通の人は、「おなかすいた」と家の人が言えば、「何か食べ物ある?」という意味だと、「推論」します。だから、選択肢2の談話も違和感がないのです。
よって、選択肢2は、推論が談話にまとまりをもたらしているといえます。
3,Yの発話は、主語が抜けています(「(渋谷は)混んでるよ」)が、それは、その前の文を構成する要素に依存して解釈されるからです。問題文の初めの具体例(「とても軽くて、よく飛んだ」)と同じです。よって、言語的要素が談話のまとまりをもたらしているといえます。
4,Yの発話も主語が抜けています「(クマのぬいぐるみは)お子さんへのプレゼントですね」ですが、3と同じ理由です。言語的要素が談話のまとまりをもたらしているといえます。
平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰの問題3のCは【文章のまとまり】です。
(11)
「とても軽くて、よく飛んだ」と言われたら、「何が?」となります。つまり、動作の主体、主語が省略されています。
よって、正解は3です。
(12)
文と文を関連づける仕組みを結束性といいます。
よって、正解は1です。
(13)
1,一文目は「彼女」のことを述べていないので、文が繋がっていません。
2,一文目は「彼女」のことを述べていないので、文が繋がっていません。
3,一文目は「彼」のことを述べている(友達)ので、文が繋がっており、代名詞「彼」が文と文の関係を表すのに使われています。
4, 一文目は「彼」のことを述べていないので、文が繋がっていません。
よって、正解は3です。
(14)
内の関係と外の関係については、平成27年度 日本語教育能力検定試験Ⅲの解説 問題3を参照。
現場指示と文脈指示については、平成23年度 日本語教育能力検定試験Ⅰの解説 問題1の(8)を参照。
・前方照応は、前を照らします。
例…僕は猫を買っている。彼女はササミが大好物だ(「彼女」が前方の「猫」を照らしている)。
・後方照応は、後ろを照らします。
例…僕が新しく買ったスマホはこれ。iPhone7です(「これ」が後方の「iPhone7」を照らしている)。
(平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(8)【指示詞の現場指示・文脈指示用法】の2も後方照応の具体例になります。)
以上より、正解は1です。
(15) 発話内の言語的要素ではなく、推論が談話のまとまりをもたらすものを選ぶ問題です。
1,Xの「熱」を、Yの「それ」が受けているので、言語的要素が談話にまとまりをもたらしています。
2,X「おなかすいた」
Y「台所にカレーがあるよ」
という2つの文には言語的要素では、談話にまとまりをもたらしていません。
まとまりがある、と思う人は、すでに推論しています。
例えば、
X「おなかすいた」Y「晩御飯食べてないの?」であるとか、
X「食べ物何かある?」Y「台所にカレーがあるよ」であれば、言語的要素が談話にまとまりをもたらしています。
一方、
「おなかがすいた」と「台所にカレーがある」は言語的要素だけを見ればまとまりがないです。
しかし、普通の人は、「おなかすいた」と家の人が言えば、「何か食べ物ある?」という意味だと、「推論」します。だから、選択肢2の談話も違和感がないのです。
よって、選択肢2は、推論が談話にまとまりをもたらしているといえます。
3,Yの発話は、主語が抜けています(「(渋谷は)混んでるよ」)が、それは、その前の文を構成する要素に依存して解釈されるからです。問題文の初めの具体例(「とても軽くて、よく飛んだ」)と同じです。よって、言語的要素が談話のまとまりをもたらしているといえます。
4,Yの発話も主語が抜けています「(クマのぬいぐるみは)お子さんへのプレゼントですね」ですが、3と同じ理由です。言語的要素が談話のまとまりをもたらしているといえます。
よって、正解は2です。