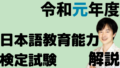試験Ⅱの問題5は、毎年、日本語学習者向けの聴解教材を聞いて複数の問いに答える問題です。
問題5でよく聞かれる問いは
①この聴解問題の特徴は?
②この聴解問題を解くために必要な○○(能力、ストラテジー、文法的知識など)は?
③この聴解問題の問題点は?
の3つです。
学習者向けの問いも音声で流れるので、実際の学習者になった気持ちで実際に聴解教材をやってみましょう。実際にやってみると、聴解問題を解くために必要な能力(②)や問題点(③)がわかります。
音声が流れる前に少し時間がありますから、そのわずかな間(ま)で、問いと選択肢を確認しなければなりません。
問題5は3つありますが、毎年1つは資料付きの問題です。資料付きの問題は資料を見ただけで答えが分かることがあるので、音声が流れる前に素早く資料をチェックしましょう。
1番 アンケートの結果
聞く前に、資料と2つの問いと各選択肢を確認。
問1 必要なストラテジー
各選択肢の必要なストラテジーを見てどんな問題かイメージ
a 自己の体験と照合する
自分の体験に照らし合わせないと解けない問題をイメージ
b 結論を予測する
結論が明らかにされていないので予測しなければいけない問題をイメージ
c 情報を関連づける。
1つの情報だけでは解けないので複数の情報を関連付けなければいけない問題をイメージ
d 事例を抽象化する。
例えば、「Aさんは英語が下手」「Bさんは英語が下手」「Cさんは英語が下手」という具体的な事例から、みんな「日本人」という共通点を見つけて、「日本人は英語が下手」と共通点でまとめること。
聞く。
最初に聴解教材の問いが聞こえます。
聴解教材の問い「子供が外で遊ばなくなった最も大きな理由は何ですか?」
資料を見ると、「スマホやゲーム」
え…
必要なストラテジーどころか、聞かなくても解けるんですが…。
慌てますが、続きを聞きます。
「『スマホやゲームをしている時間が長い』が…45%を占めています」という情報だけでは、答えは出ません。「次いで…が18%」の情報を合わせることで、残りは37%だから、最も大きいのは45%の『スマホやゲーム』だとわかります。
「45%」と言う情報と「次いで…18%」という情報を関連付けています。
よって、答えはc
問2 この聴解教材の問題点
音声を聞かなくても、グラフを見たら一目瞭然なのですが…。スマホやゲーム…
よって、答えはb
2番 電話の会話
聞く前に2つの問いと各選択肢を確認。
問1 必要な文法的知識
a 言いさしとぼかし表現
言いさしとは、「明日、会える?」「明日は忙しくて…」など、文の途中で終わること。日本語会話で多用される。
ぼかし表現とは、「善処します」など具体的によくわからない表現のこと。気が進まないときによく使われる。
b 終助詞と伝達表現
終助詞とは、「行くよ」の「よ」、「行くね」の「ね」など、文の終わりで気持ちを伝える助詞。
伝達表現とは、「伝えてもらえますか」など伝達するための表現。
c モダリティと推量表現
モダリティとは、文の主観的な部分。文は客観的な部分(命題)と主観的な部分(モダリティ)にわけられる。
例)食べてください
「食べ(る)」が命題、「てください」がモダリティ(依頼)
推量表現とは、「~だろう」などよくわからないことを判断するときに使う表現。
d ヴォイスと受益表現
ヴォイスとは、だれの声(voice)か。つまり誰の立場からの文か。態(たい)ともいう。能動態(行為をする人からの文)、受動態(行為をされる人からの文)、使役態(行為をさせる人からの文)などがある。
受益表現とは、「くれる」「もらる」など、誰かが利益(ベネフィット)を受けることを表す文。授受表現の一つ。授受表現には、与益表現と受益表現がある。
与益表現とは、「あげる」「やる」など、誰かにが利益(ベネフィット)を与えることを表す文。受益表現には物の授受と行為の授受がある。
物の授受とは、「くれる」「もらう」「あげる」。
例)プレゼントをもらった。
行為の授受とは、「てくれる」「てもらう」「てあげる」
例)プレゼントを買ってもらった。
聞く。
最初に、この聴解教材の問いが聞こえてます。
聴解教材の問い「この後、誰が誰に電話をしますか」
聴解教材の選択肢
- ラーメン屋の男の人から魚屋の男の人に電話をします。
- ラーメン屋の女の人から魚屋の男の人に電話をします。
- 魚屋の男の人からラーメン屋の男の人に電話をします。
- 魚屋の女の人からラーメン屋の男の人に電話をします。
「誰が誰に電話をするか」の判断には、「電話させるわね」「電話させてもらってもいいですか」という表現の意味を理解していなければなりません。
「させる」「させて」は使役態、つまりヴォイス。
「てもらって」は受益表現。
よって、答えはd
問2 この聴解教材の問題点
ここでおかしいことに気づいたでしょうか。そうです。上の選択肢には「魚屋」「ラーメン屋」という言葉が出てきていますが、会話では一言も出てきませんでした。
いったいいつから我々はラーメン屋と魚屋の会話だと理解していたのか?
そう。
「来々軒(らいらいけん)」→ラーメン屋
「魚政(うおまさ)」→魚屋
と脳が勝手に情報を関連付けていたのです。
われわれ日本人にとっては難しくない処理。
ですが、外国人にとってはどうでしょうか?
「らいらいけん」は町中華にありそうなお店。
「うおまさ」は魚に関するお店っぽい。
という特定の語に関する社会文化的知識が必要となります。
よって、答えはb
なお、
縮約形とは、「おいておく」→「おいとく」のように、元の形を縮めた形のこと。
スピーチレベルシフトとは、「です」「ます」で丁寧に話していたのに年齢や出身が同じだとわかって、タメ語(カジュアルな言葉)で話すように、会話の途中で丁寧のレベルを変えること。
例)「どちら出身ですか?」「福岡です」「え、俺も同じ!」
縮約形もスピーチレベルシフトも聴解問題でよく出てきます。
知らなかった! という人は下記の記事をどうぞ。
3番 男女の会話
聞く前に2つの問いと各選択肢を確認。
問1 必要な能力
各選択肢から問題をイメージ
a 特定の接続表現から談話展開を推測する能力
例)「ところで」→話題が変わる、「でも」→反対のことをいうなど特性の接続表現からその後の会話の展開を予測。
b 情報を絞り込みながら話を聞き取る能力
情報が多すぎるから絞り込まなきゃいけないのかな?
c 細部まで正確に聞いて因果関係を捉える能力
「ので」「よって」など因果関係を表す言葉に気を付けたほうがいいかな?
d 情報を時系列に沿って並べ直す能力
聞く。
聴解教材の問い「二人はどのプランを選びましたか」
聴解教材の選択肢
- シンプルプラン
- のんびりぷらん
- よくばりプラン
- リラックプラン
この聴解教材を解くには
「(よくばりプランは)…へえ、すごいねえ。…でも、12000円は高いなあ」
「おお、それもいいねえ。でも、やっぱり贅沢に行かない?」
という男性の言葉を理解する必要があります。
「でも」という逆接の「接続表現」を使っているから、男の人が選んだのは女の人が提案したプランじゃないだろうと「談話展開を推測する能力」が必要です。
よって答えはa
問2 必要な語
この聴解問題を解くためには
「おお、それもいいねえ。でも、やっぱり贅沢に行かない?」という男性の言葉と
「よくばりプラン」という選択肢を結び付けることができなければなりません。
「贅沢」の意味が「よくばり」に似ていることを理解していなければなりません。
よって答えはc