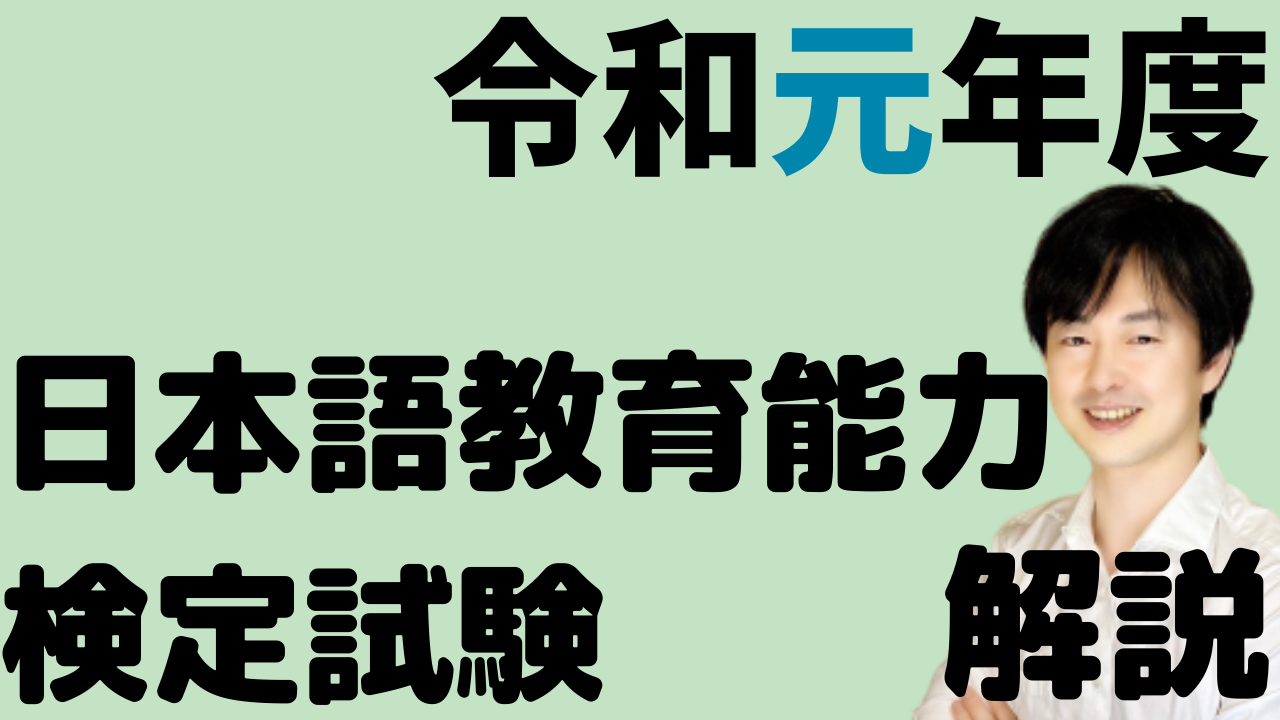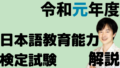合格するための過去問解説講座をYouTubeで見る
問1の解き方
1.
エラー
理解しておらず何度も間違える
ミステイク
理解しているがたまたま間違える
★授業でどう使う?
エラーかミステイクか実際の授業では判断がむずかしいときも。誤用だけでなく正用にも注目するとか。自分で直せるか確認するとか。
例)
S「明日は猫カフェに行きようと思います」
T「行きよう?」
S「あ、行こうと思います」
グローバルエラー
コミュニケーションに支障が出るエラー
例)猫が撮った写真を見たいです。 を? と?
ローカルエラー
コミュニケーションに支障が出ないエラー
例)猫カフェで行く。
★授業でどう使う?
グローバルエラーなら直すけど、ローカルエラーなら直さないとか。
どこまで直すかは学習者を見て。
助詞にこだわりすぎるのはよくないが、
定着化の問題もある。
定着化とは?
誤用が定着してしまうこと。
前は化石化と言っていた。
最近は定着化。
例)ロスタイム→アディショナルタイム
よって、答えは2
問2の解き方
2.中間言語とは
ミーのメニメニライクなブックは、オーダーのメニーなクッキングストアですね。
訳:私の大好きな本は「注文の多い料理店」です。
第一言語(母語)でも第二言語(外国語)でもない中間の言語。
学習者の中間言語は、ちゃんと話せたり(正用)、間違えたり(誤用)を繰り返して変わっていく。
習得順序とは、どんな順序で文法を習得するか。
日本語の習得順序は学習者のタイプによって異なるので厳密には決まっていない。
★授業でどう使う?
日本語学校の多くは
「ます形」→「普通形」の順番で教えている。
食べます→食べる
飲みます→飲む
素朴概念とは、日常の経験から得た知識や概念。誤りも多い。
⇔科学的概念:客観的な仮説検証によって構成
よって、答えは3
問3の解き方
3.忘れないように復唱しても忘れる件
記憶には、ワーキングメモリと長期記憶がある。
ワーキングメモリ:一時的に情報を保持
長期記憶 :半永久的に覚えている。
インプットされた情報を忘れないように
ワーキングメモリ上にとどめておいたり、長期記憶に転送する方法をリハーサルという。
①維持リハーサル:ワーキングメモリ上に維持
書いたり声に出したり心の中で繰り返す。長期記憶は期待できない。
②精緻化リハーサル:イメージしたり、知ってることと関連付けて長期記憶に転送
1)母語に対応する語と関連づける。キーワード法など
2)文を作成する。
3)類義語と結び付ける。
★授業でどう使う?
維持リハーサル(単純に繰り返す練習)ではなく精緻化リハーサル(イメージ化、関連付け)をしよう。
例)漢字を覚えるために…
△繰り返し書かせる:維持リハーサル
〇イメージしながら1回書く:精緻化リハーサル
「ウ…ハムの心は窓ですか」など。
1.維持リハーサル
2.精緻化リハーサル
3.精緻化リハーサル
4.精緻化リハーサル
よって、答えは1
問4の解き方
4.ビリーフとは、信念。僕が信じているやり方。
認知スタイルとは、情報をどうやって処理するか。個人によって異なる。
場依存:関連付けてとらえる。コミュニケーションが得意。
場独立:独立してとらえる。文法など形式中心の学習が得意。
視覚型か聴覚型か/熟慮型か衝動型か
★授業でどう使う?
〇ビリーフ
学習者には個々のビリーフがあるので
教師のビリーフを押し付けない。特に年長者
〇認知スタイル
学習者が得意なやり方を提供する。
視覚か聴覚か? 会話か文法か?
1.ステレオタイプ 例)ラテン系は明るい。
2.ラポール
平成29年度試験Ⅰ問題8問1「相互の信頼関係」
3.ビリーフ
4.認知スタイル
よって、答えは3
問5の解き方
5.日本人の英語がひどいのは自信がないから
情意フィルター仮説
不安や恐れが大きいと言語習得が進みにくい。
接触するインプットと吸収するインプットの間には情意(言語に対する態度、自信、不安など)のフィルターがある。
3.認知スタイルの衝動型
4.情意フィルター仮説
事前に説明するのは最小限。
認知的負荷は学習効率を落とす。
よって、答えは4