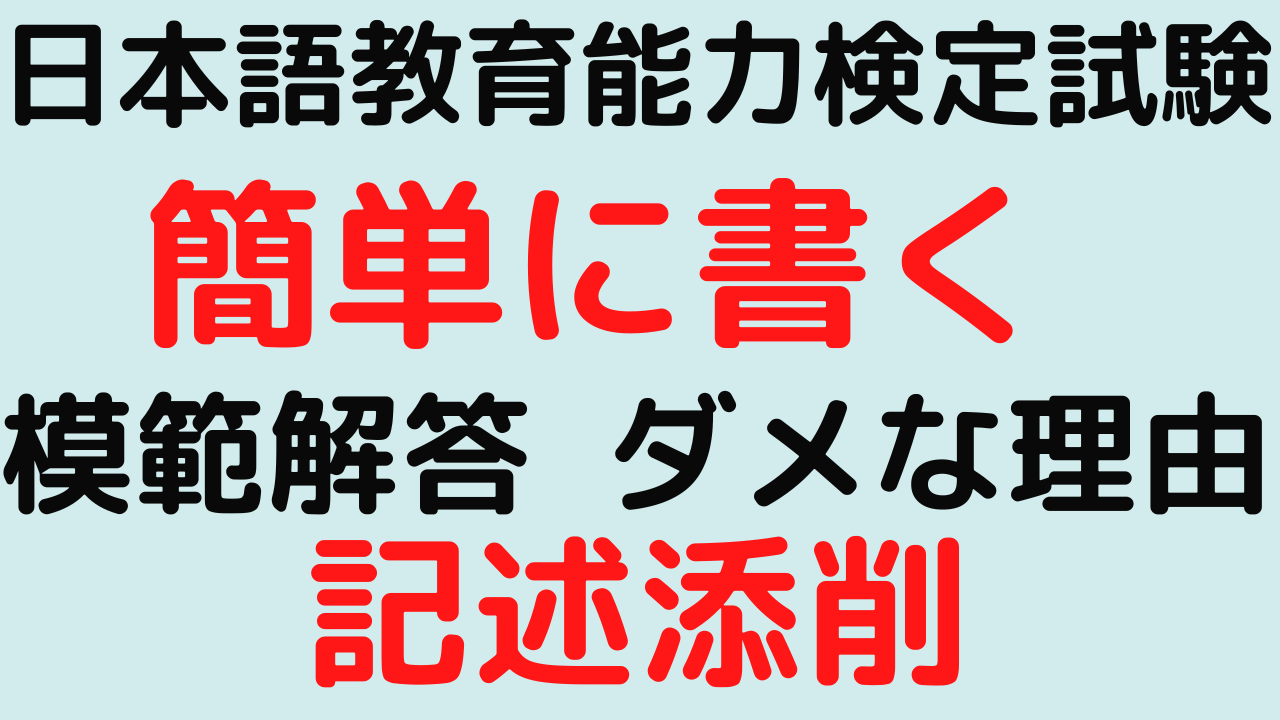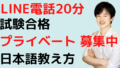- 記述問題6ヶ条
- 公式の解答例の問題点
- 平成30年度の記述のポイント
- 令和元年度の記述問題のポイント
- 令和2年度の記述問題のポイント
- 令和3年度の記述問題のポイント
- 令和4年度の記述問題のポイント
- 以下は2016年に公開した『苦手な人のための記述問題対策』の改訂版になります。
- 問いに応える
- 平成27年度記述式問題の問いに応える
- 問題文の言葉をなるべく使う
- 平成27年度記述式問題の言葉をなるべく使う
- 反対意見の根拠に配慮する
- 平成27年度記述式問題の反対意見の根拠に配慮する
- 問題文の言葉を解釈する
- 平成27年度記述式問題文の言葉を解釈する
- 抽象論・一般論に加え、具体論・個別論も書く
- もう1つのポイント
- 問題作成者と採点者の気持ちになる
- 勉強しすぎて失敗するパターン
- 2023年度日本語教育能力検定試験記述が書けるようになる会
- 記述対策
記述問題6ヶ条
これは書く順番ではなく、記述を書く前と書いた後にチェックする項目。以下ができているか確認
1,問いに応える。
2,問題文の言葉をなるべく使う。
3,反対意見の根拠に配慮する。
4,問題文の言葉を解釈する。
5,抽象論・一般論に加え、具体論・個別論も書く。
6,問題作成者・採点者の気持ちになる。
公式の解答例の問題点
①年度によって書き方が異なりパターン化できない。
②知っておくべき知識が多すぎて真似できない。
③言葉が難しくて真似すると失敗する。
→パターン化して少ない知識で誰にでもわかる答案を書く。
日本語教師になりたいなら、難しい言葉を書けるようになるのではなく、誰にでもわかるやさしい言葉で説明できるようになったほうがいい。
今から記述の対策をしますが何から始めたらいいですか?
①過去の問題を解く。
②ハマのYouTube記述添削動画を見て、他の人の回答の良い点悪い点を参考にする。
③赤本(日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド)で、記述の書き方を学ぶ(第5班だと第7部記述問題p526~)
平成30年度の記述のポイント
①「他の学生からコメントをもらっても意味がない。作文は先生に直してもらいたい」という要望についてどのように対応しますか。
→「この要望に対して以下のように対応する」
② 次回からの作文の授業をどのように進めますか。
→「次回からの作文の授業を以下のように進める」
③「理由」
→「なぜなら」
④「ピア・レスポンス」という活動にどのような意義があるのか。
「ピア・レスポンス」には〜のような意義がある。
令和元年度の記述問題のポイント
①「談話の全体像を把握するためには、あなたはどのようなスキルが必要だと思いますか」
→「談話の全体像を把握するためには○○のスキルが必要だと思う」
②そのスキルを高めるために、どのような教室活動をすると効果があると思いますか。
→「○○のスキルを高めるために、△△をすると効果があると思う」
③必要とされるスキルと、その養成に必要な具体的活動内容を示すとともにその活動がなぜ「必要とされるスキル」の養成につながるのかを記述
→「なぜなら~」
令和2年度の記述問題のポイント
① こうした意見について日本語教育に関わる者としてどのように考えますか。
~のように考える
② キーワードをどのような意味で使っているか分かるように
→キーワードの定義・意味を書く必要
③ キーワードを1つ以上選び、関連付けて
→複言語主義、言語権、規範主義
・「複言語主義」は平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問2で登場
・「規範主義」は平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D(16)で登場
令和3年度の記述問題のポイント
① 知識伝達の段階においてどのような動画を用意しますか。
② 60分の授業時間内でどのような活動を展開しますか(②´反転授業のメリットが十分活用できるような計画)
③ 上級文法クラスにおいてその活動が効果的と考えられる理由
→この3つが書けているか書いた後に確認
令和4年度の記述問題のポイント
① 学習者の自己評価について自分がどのように考えるか?
② 意義と問題点を検討
③ どのような形で自己評価を促すか(→①は肯定的に書く)
内発的動機づけを促す例は平成30年度試験Ⅰ問題9問5「クラスメートと協働的に学ぶこと」
④ 意味がわかるようにキーワードを複数取り上げる→意味を確認
以下は2016年に公開した『苦手な人のための記述問題対策』の改訂版になります。
日本語教育能力検定試験の記述式問題の配点は20点あります。大きいですね。
ですが、採点基準が公開されていないので、対策をするのが難しいです。
書き方が全然わからないという人もいます。
そこで
誰でも簡単に書けるように
どんな問題でも書けるように
記述式問題の書き方を分かりやすくまとめました。
私は、日本で最も難しいテストと言われた旧司法試験の論文式試験に大学4年生合格しました。
その後は、論文式試験対策講座の講師をしたり、答案の添削をしたりしました。
2020年のYouTubeライブでは、のべ95人の日本語教育能力検定試験の記述問題を添削しました。
2021年にはこちらの動画の通りさらに多くの日本語教育能力検定試験記述答案を見ました。
2022年にもメンバー限定ですが日本語教育能力検定試験の記述添削を行いました。
そのノウハウを全てお見せします。
私が旧司法試験に合格できたのは『論文6ヶ条』という論文を書くマニュアルを開発したからです。
旧司法試験論文試験のために作成した論文6ヶ条を日本語教育能力検定試験記述試験のために一部修正し、ここに公開します。
記述問題6ヶ条
1,問いに応える。
2,問題文の言葉をなるべく使う。
3,反対意見の根拠に配慮する。
4,問題文の言葉を解釈する。
5,抽象論・一般論に加え、具体論・個別論も書く。
6,問題作成者・採点者の気持ちになる。
この記述マニュアルを実際に平成27年度の記述式問題を書きながら解説します。
私のオススメする記述問題対策は、
初心者・苦手な方向けのマニュアル化した記述問題の書き方になります。
上級者の方、記述が得意な方には不要なマニュアルだと思います。
その点、ご了承ください。
以前の記述添削会はこちらから見ることができます。
問いに応える
日本語教育能力検定試験Ⅲ記述式問題の書き方その1は【問いに応える】です。
旧司法試験の答練(記述式問題)の採点や、論文試験講座の講師をしていたときにとても驚いたことがあります。
問いに応えている人があまりにも少ないのです!
自分の知識を自慢したいのか、問われていることが苦手なので避けたのか、無意識の天然さんなのか、理由は様々だと思いますが、
そんなこと聞いてないよ!
と言いたくなる答案があまりにも多い。
だから、記述式問題で最も大事なのは『問いに応える』ことです。
『答える』ではなく『応える』を使っているのは、
問いに対応した文章を書いてくださいという意味です。
平成28年度日本語教育能力検定試験 合格するための本の記述式問題(162頁)を先ほど読んだのですが、恐ろしいことが書いてありました。一部引用します。
『こう書かなきゃ、なんて思わず、採点者をおもしろがらせたいという気持ちで、創意工夫を凝らしてみてください!』
やめてください。
ほとんどの方はその『創意工夫』を失敗します。
パターンに当てはめて書く論文はもう飽き飽きだよ。オレは論文の達人なんだ。
というレベルの方以外は、真に受けてはいけません。
立川談志も言っています。
『型ができていない者が芝居をすると型なしになる。メチャクチャだ。型がしっかりした奴がオリジナリティを押し出せば型破りになれる。』(立川談春『赤めだか』72頁)
まずは、記述問題の型(パターン)を身に着けましょう。
問いに応えなきゃ、という姿勢で書いてください。
では、問いに応えるには、具体的にどうすればいいのでしょうか?
冒頭で、問題文の問いの言葉を使って答えを書くのです。
平成27年度日本語教育能力検定試験の公式解答は、「ディベート」の目的から書き始めていますが、真似してはいけません。
これは、初心者の方、苦手な方が失敗するやり方です。
初心者の方、苦手な方が、問いに対応せず書き始めると、論点がずれる恐れがあります。
必ず、最初の一文で問題文の問いの言葉を使って答え(自分の意見)を書いてください。
問いに対応した答えが思い浮かばないよ、オレは自分の書きたいことを書くんだ。
そんな頑固な方も最初の一文だけは問いに対応させてください。
例えば、
『あなたが昨日の夜、食べたものは何ですか? その理由とともに200字程度で記述してください』
という問題が出たときに、あなたはどんな言葉から書き始めますか?
考えてみてください。
昨日の夜、何を食べたか思い出せないときはどうしますか?
「やばい、夜に何を食べたか忘れた(問いに対応した答えが思い浮かばない)! 仕方ないから昼に何を食べたか書こう(自分の書けることを書こう)」
このように判断して
「私は昨日の昼、吉野家の牛丼を食べた。なぜなら、私は吉野家をこよなく愛しているからだ。そもそも私が吉野家と出会ったきっかけは〜」
と書き始める人がいます。
昨日の夜のことを聞いているのに、昼のことを書く。
アホかと思うかもしれませんが
実際の試験ではこの失敗が多いのです。
聞かれていることとは違うことを答えて
「何言ってるんだコイツ」
と採点者を呆れさせることになってしまいます。
一方で、同じ状態(昨日の夜に何を食べたか忘れたので、問題文に対応した答えが書けない)でも、
「私は昨日の夜、何も食べなかった。昼に吉野家の牛丼を食べたからだ〜」
のように、最初の一文を問いに対応させることで、
「この人は問いに応える姿勢があるな」
と採点者にアピールできるのです。
本試験で、知識が足りなくて問いに対応したことが書けない、思い浮かばない、と感じても、
最初の一文は、上の例のように、問いの言葉を使って書いてください。
それでは、平成27年度記述問題の問いは何でしょうか?
冒頭はどのように書きだしますか?
私の答えは見る前に、まずは自分で書いてみてください。
平成27年度記述式問題の問いに応える
平成27年度記述問題にはメインの問いとサブの問い、合わせて2つの問いがあることに注意してください。
メイン『あなたはこの申し入れを受け、今後このクラスでの活動をどのように進めていきますか』
サブ『「 論理的思考能力を高める」ためには何が必要かについて、あなた自身の考えも明示してください」
記述問題が苦手な方には、このように問いが複数あるときに、どちらか一つの問いに応えるだけで満足してしまう人がいます。
ダメです!
忘れないように、問題文の問いには、○で囲むなど印をつけてください。
平成27年度記述問題の書き出しは以下のとおりになります。
メインの問い『あなたはこの申し入れを受け、今後このクラスでの活動をどのように進めていきますか』
解答『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。』
太字部分が問題文の問いの言葉を使っている部分です。それ以外の部分は好きに書いてください。もちろん反対意見でも構いません。
このように、冒頭の一文で、問いに対応させて答え(自分の意見)を書けば、採点者に対して、問いに応えていることを明示的にアピールできます。実際の受験生の答案は問いに応えていないものがあまりに多いので、このアピールはとても大事です。
問題文の言葉をなるべく使う
日本語教育能力検定試験Ⅲ記述式問題の書き方その2は【問題文の言葉をなるべく使う】です。
記述式問題の採点をしていると、問題文にヒントとなるキーワードが散りばめられているのに、それを使わずに、わざわざ自分の言葉で書こうとする人がたくさんいます。
オリジナリティをアピールしたいのでしょうか?
よっぽど優秀な方以外は失敗しますので、やめてください。
せっかく問題文があるんですから最大限利用しましょう。
平成27年度記述式問題の言葉をなるべく使う
平成27年度日本語教育能力検定試験の記述問題も、問題文が9行もあるので、「これはありがたい」と思って問題文の言葉をできるだけ流用してください。問題文の言葉を可能な限り使うことで、問いに応える姿勢を採点者にアピールできます。
【問題文の言葉をなるべく使う】という視点で、平成27年度記述式問題の解答の続きを書きます。
まず、書き出しは、
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。』
でした。
この一文も問題文の言葉をしっかり使っていますね。
冒頭で簡潔に答え(自分の考え)を書いたら、次は簡潔に理由を書きます。
問題文に使える言葉はないかと探すと、ディベートを取り入れた目的として「論理的思考能力を高める」というキーワードがありました。このキーワードは、サブの問いにもなっていますので、【問いに応える】という意味でも、必ず使わなければならない言葉です。必ず使わなけばならない言葉はなるべく早く使ったほうがいいです。後にとっておくと、忘れたり、時間が足りなくなったりしますから。
最も大事なメインの問いに一文目で応え、次に大事なサブの問いに二文目で応えます。
合わせると以下の答えになります。
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。』
太字部分がそれぞれ、
メインの問い『あなたはこの申し入れを受け、今後このクラスでの活動をどのように進めていきますか』
サブの問い『「 論理的思考能力を高める」ためには何が必要かについて、あなた自身の考えも明示してください」
という問題文の言葉を使っています。
反対意見の根拠に配慮する
日本語教育能力検定試験Ⅲ記述問題の書き方その3は【反対意見の根拠に配慮する】です。
自説とその理由付けを簡潔に書いたら、次は、反対説へ配慮しましょう。
自分が柔軟で心の広い人間であることを採点者にアピールするのです。
例によって、平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲの問題17(記述式問題)で具体的に説明します。
前回までの記述式問題対策で、
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。』
まで書けました。
次に、反対説を書くのですが、
この問題では何が反対説になるでしょうか?
答えを考えた後、続きをお読みください。
平成27年度記述式問題の反対意見の根拠に配慮する
記述問題対策第2条【問題文の言葉をなるべく使う】に従って、問題文を見てみると、
ある学習者が「自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは精神的に苦痛である。どうしてこのような活動をするのか」と言ってきました。
というディベートに対する反対意見を発見しました。
これを使います。
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。
確かに、自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは、精神的に苦痛かもしれない。』
※太字部分が問題文の言葉を使っています。
これで、反対意見に配慮して、心の広い人間であることを採点者にアピールできました。
しかし、記述問題対策第3条には【反対意見の根拠に配慮する】と書きました。
そこには理由があるのですが、第4条【問題文の言葉を解釈する】とも関わってくるところなので、第4条で説明します。
問題文の言葉を解釈する
日本語教育能力検定試験Ⅲ 記述問題の書き方その4は【問題文の言葉を解釈する】です。
そろそろ疑問を抱いた方が、おられるかもしれません。
「誰でも簡単に高得点が狙える記述式問題の書き方を教えると言っておきながら、その解答は問題文をコピペしてるだけじゃないか。こんなんで高得点が狙えるのか?」
安心してください、狙えます。
大学の入学試験に始まり、会社の採用試験、教職員採用試験、司法試験、日本語教育能力検定試験など、様々な分野の試験において、記述式問題は登場します。
私は全ての分野の記述式試験を把握しているわけではありません。
しかし、いくつかの分野の記述式問題を仕事あるいは個人的に添削させて頂いたことはあります。
共通して言えるのが、問いに応えている答案が少ないということ。
苦手な方が書く記述答案は問いに対応していないのです。
「問いに答えてください」と初めは抽象的に指摘していたのですが、それではあまり効果がありませんでした。
苦手な方は「問いに答えるとはどういうことか」が分かっていなかったのです。
そこで私が生み出したのが、1行目は問題文の問いの言葉をそのまま使って答えを書くこと。2行目以降も問題文の言葉をなるべく使うこと。
この具体的な指導によって、記述式問題が苦手な方でも問いから離れることは少なくなりました。
問題文の言葉をコピペすることで、土台が固まったからです。
しかし、問題文の言葉を書き写すだけだと字数が足りませんし、
「コイツ何も考えていないんじゃないか?」
と採点者に思われてしまいます。
そこで、固めた土台の上に自分の考えを築くのです。
「苦手な人でも簡単に書ける、パターン化できると言っておきながら、結局自分の考えを書けかよ、それが苦手なんだよ」
と思った方もおられるかもしれません。
安心してください、すでに土体はあるのです。
苦手な方が今まで書けなかった、書いても点数が伸びなかったのは、目印も何もない広大なグラウンドに、いきなり自分の力で家を建てようとしたから失敗したのです。
最初から自分の考えを書くのではなく、まずは問題文の言葉を尽くして答案の方向性を定める点がこのメソッドのポイントです。
1,問いに応える。
2,問題文の言葉をなるべく使う。
3,反対意見(の根拠)に配慮する。
この3点で組み立てたのは堅固な土台ですから、よほどのことを書かないかぎり問いから外れることはありません。今こそ、あの言葉を思い出しましょう。
『こう書かなきゃ、なんて思わず、採点者をおもしろがらせたいという気持ちで、創意工夫を凝らしてみてください!』
石黒圭教授(平成28年度日本語教育能力検定試験 合格するための本の記述式問題162頁)の御言葉です。
自信がなくても、思いついたように書けばいいのです。すでに解答の枠は作ったので、その中で好きに遊べばいいのです。
とは言っても指針は必要だ。
そんなわけで、残りの三条があります。
記述問題対策第4条【問題文の言葉を解釈する】
どういうことか?
例によって平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲの問題17(記述問題)を使って、具体的に説明します。
前回までに書いた答案は以下のとおりです。
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。
確かに、自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは、精神的に苦痛かもしれない。』
反対意見まで書きましたので、さっそく反対意見を解釈しましょう。
この反対意見は学習者から出たのですが、どうして学習者は「自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは精神的に苦痛」だと感じたのでしょうか?
考えた後、続きをお読みください。
平成27年度記述式問題文の言葉を解釈する
私の解答は、
「普段とは異なった視点で物事を考えなければならないからだ」
です。
もちろんこれが絶対の正解ではありません。自分が思ったことを書けばいいのです。
何も思い浮かばなかったら?
書かなくても構いません。
問題文から反対意見を書き写すだけでいいです。
公式解答も問題文の反対意見を書き写しているだけです。
しかし、ですよ。
単に、反対意見に配慮するのではなく、
反対意見が出てきた原因、その根拠にまで配慮したほうが、
議論が深まるとは思いませんか?
反対意見のことを真剣に考えているとは思いませんか?
なので私は
「反対意見に配慮する」
ではなく、
「反対意見の根拠(理由・原因)に配慮する」
ことを勧めています。
反対意見は問題文に書かれていましたが、その根拠(理由・原因)は書かれていませんでした。
そこで、
問題文の言葉(ここでは反対意見)を解釈した(ここでは反対意見が出てきた原因を探ること)のです。
最後に平成27年度記述式試験のここまでの解答をまとめます。
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。
確かに、自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは、精神的に苦痛かもしれない。普段とは異なった視点で物事を考えなければならないからだ。』
抽象論・一般論に加え、具体論・個別論も書く
日本語教育能力検定試験Ⅲ 記述問題の書き方その5は【抽象論・一般論に加え、具体論・個別論も書く】です。
今回はさっそく平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲの問題17(記述問題)を使って、具体的に説明したいと思います。
前回までに書いた答案は以下のとおりです。
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。
確かに、自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは、精神的に苦痛かもしれない。普段とは異なった視点で物事を考えなければならないからだ。』
このあと何を書きましょうか?
自説→その理由→反対説→その根拠→?
ときたら……
もちろん。
反対説の根拠を叩くのです。
反対説(の根拠)を潰すことで、自説が補強できます。
お好きなように反対説を鞭打ってください!
私は以下のとおり書きました。
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。
確かに、自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは、精神的に苦痛かもしれない。普段とは異なった視点で物事を考えなければならないからだ。
しかし、それこそがディベートの目的である。自分と違う意見を述べるには、まず自分を理屈で納得させなければならないので、いつもと違う視点で深く考えなければならない。すると、物事を多角的に見る力が身につき、論理的思考能力も高まるのである(←メインの問いに対する答えを論じながら、サブの問いに対する答えも補強しています)。日本語クラスにいるであろう他文化の人間との交流にも役立つはずだ。』
いけない。
記述問題対策を説明していたのを忘れて、最後まで書いてしまうところでした。
とりあえずここまでにいたします。
読み返して思ったのですが、無駄に字数を使いすぎていますね。
「普段とは異なった視点で物事を考えなければならない」
「いつもと違う視点で深く考えなければならない」
このあたりが重複しています。
完璧を求めるならばどちらかを削除して、論旨をスッキリさせたいところですが、
記述問題で大事な考え方の一つは、
完璧な答案を書こうとは思わないこと
なので、これでよしとします。
完璧な答案を書こうとすると、書けなくなってしまう・時間が足りなくなってしまうことが多いので、記述対策前三条で基礎を固めたあとは自由に書くことが大事なんですね。
多くの人が不十分な基礎固めさえしっかりできていれば、高得点は狙えます。
と言っても指針は必要だ。
そんなわけで、第5条の登場です。
【抽象論・一般論に加え、具体論・個別論も書く】
上記の答案を見てみると、抽象論・一般論・理想論が多いですね。
論理的思考能力が高まるだの、多角的な視点だの。
もちろん、抽象論・一般論も大事なんです。
しかし、それに加え、具体論・個別論という異なった視点から自説を補強することで、さらに説得力が増すんですね。
ここでも多角的な視点が大事なんです。
何も考えずに書いていると、抽象的なことばかり書くか、具体的なことばかり書くか、どちらかになりがちなので、第5条があります。
本問のように問題文が長い場合、自説を補強するための抽象論か具体論、いずれかのキーワードが問題文に紛れ込んでいることが多いのですが、この問題では前者です。
自説は、「ディベートを取り入れる」ということですが、
その抽象的(一般的)理由付け「論理的思考能力を高める」という文が問題文にありました。
問題文の言葉をなるべく使っていった結果、抽象論に偏っていました。
なので最後は具体論を書いて、バランス良く締めたいと思います。
ちなみに、さきほど書いた最後の一文は、ちょっと具体的ですね。
『日本語クラスにいるであろう他文化の人間との交流にも役立つはずだ。』
ここでも問題文の言葉(太字部分)をさりげなく使って、問題文をしっかり読んでいることを採点者にアピールしました。
ただし、問われていることとは離れているので、字数が足りなければ削除すべき部分です。
さて、
最後の段落を書くにあたって、
一つの指針は具体的に書くことですが、
実はもう一つ、書くべきポイントがあります。
それは何でしょうか。
お考えの上、続きをお読みください。
もう1つのポイント
もう一つのポイントは、反対意見への配慮です。
私の書いた答案を読んでみると、
反対説に配慮したと言っておきながら、結局それを自説の理由付けに使っているだけで、
譲歩は一切していないのですね。
記述問題によってはそれでいいのですが、
本問の場合、反対説は学習者から出ています。
学習者の意見を、滅多打ちにして、ハイ終わり。
は、教師としてどうなんでしょうか?
よろしくはなさそうです。
だから、ここでは譲歩して、
学習者の意見に耳を傾けることのできる、心の広い教師であることを、採点者にアピールしたいと思います。
しかも抽象論ばかり書いていたので、具体的に譲歩する必要があります。
それでは、具体的な譲歩を書いてみます。
『もちろん、学習者の申し入れに対する配慮も考えたい。例えば、最初の授業では自分と同じ立場で立論させる。そのかわり、次の授業では反対の立場に立たせる。「自分で自分の意見を論破できるかな?」というのは面白そうで受け入れられやすいのではないか。』
どうでしょうか。
一気に具体的になりましたね。
このように抽象論と具体論、両方の視点から論じることで、解答に厚みが生まれます。
最後に解答をまとめます。
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。
確かに、自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは、精神的に苦痛かもしれない。普段とは異なった視点で物事を考えなければならないからだ。
しかし、それこそがディベートの目的である。自分と違う意見を述べるには、まず自分を理屈で納得させなければならないので、いつもと違う視点から深く考えなければならない。すると、物事を多角的に見る力が身につき、論理的思考能力も高まるのである。日本語クラスにいるであろう他文化の人間との交流にも役立つはずだ。
もちろん、学習者の申し入れに対する配慮も考えたい。例えば、最初の授業では自分と同じ立場で立論させる。そのかわり、次の授業では反対の立場に立たせる。「自分で自分の意見を論破できるかな?」というのは面白そうで受け入れられやすいのではないか。』
記述問題に対する解答は以上のとおりです。
問題作成者と採点者の気持ちになる
記述試験のときは、受験生という立場を忘れてください。
自分が、問題作成者・採点者になった気持ちで臨んでください。
どうしてこんな問題を日本語教育能力検定試験の記述問題として出題したのだろう。
この言葉が使われているのはどうしてだろう。
自分が採点者だったら、どんなことを評価するだろう。
どのように書けば採点しやすいだろう。伝わるだろう。
問題作成者・採点者の気持ちを頭に入れた状態で問題文を読み、解答を書いてほしいのです。
そうすれば客観的な視点で自分の答案を眺めることができます。
自分とは離れた視点から文章を組み立てることが、論理的な文章を書くコツだと私は思います。
これが第6条【問題作成者・採点者の気持ちになる】の意味です。
そうだ。
忘れるところでした。
JEESのウェブサイトに、出題者の言葉を見つけましたので、ここに引用します。
『記述問題は、前回(平成15年)の試験改定時に示された「日本語教育は広い意味でコミュニケーションそのものである」という観点から、論理性と日本語力を測るものとなります。測定の対象となるのは主張の正当性ではありません。主張を正確に説得力をもって相手に伝えられるかどうかを、書記言語の側面から測定します。』(日本語教育能力検定試験「よくある質問」より)
読み手の視点で取り組めば、自分の主張を相手に伝えられる文章が書けると思います。
反対説の根拠に配慮して、抽象論と具体論、二つの観点から論じれば、説得力を持った文章が書けると思います。
最後に、今までの記事でお伝えしきれなかったポイント・重要なので繰り返したいポイントをまとめて、記述問題対策を終えたいと思います。
1,問題文に印をつける
問題文を読んだときに、①使えそうなキーワード、②問われていること、この2点は必ず線を引くなり、丸で囲むなりして、印をつけてください。
なぜか?
何を書くか、構成を考えているうちに忘れてしまうからです。
特に問いが複数あるときは、一つの問いのことを考えている間に、別の問いのことを忘れてしまいがちなので、必ずマークをつけて、1,2,と数字を書き込んでおくことを強くオススメします。
2,記述問題で一番大事なのは書き出し
書き出しを制するものは記述問題を制します。
記述式試験に苦手意識のある方は、公式解答のような書き方を真似しないでください。問題文の問いの言葉を使って自分の意見を書いてください。書き出しを誤ると、問いからずるずる離れていく恐れがあります。
問いの言葉を使って、問いに対応させましょう。
3,最後のまとめは字数調整に使う
市販されている論文(記述式)問題の書き方には、冒頭に自分の立場を述べ、最後も自分の立場を主張して締めるというサンドウィッチ構成を推奨しているものが多いと思いますが、日本語教育能力検定試験の記述問題においては、最後のまとめ(自説の再主張・問いへの再回答)は、必須とは思いません。
なぜか?
字数が足りないからです。
たった400字しかないのに、書くべきことは多いので、最初と最後、二度も自説を書くスペースはなかなか作れません。
平成27年度記述問題の公式解答も、一段落目でサブの質問に対する自説の主張、二段落目で反対説。三段落目でメインの質問に対する自説の主張という構成になっており、サンドウィッチ型ではありません。
私がオススメした、苦手な人でも簡単に高得点が狙える記述問題の書き方は、冒頭で自分の立場を書きます。最後のまとめは、字数が余れば、問いに対応する形で書いてください。
私の解答例で説明すると、
『私は今後もこのクラスでの活動にディベートを取り入れたい。論理的思考能力を高めるにはディベートが必要だと考えるからだ。
確かに、自分の考えとは違う立場で意見を述べるのは、精神的に苦痛かもしれない。普段とは異なった視点で物事を考えなければならないからだ。
しかし、それこそがディベートの目的である。自分と違う意見を述べるには、まず自分を理屈で納得させなければならないので、いつもと違う視点から深く考えなければならない。すると、物事を多角的に見る力が身につき、論理的思考能力も高まるのである。日本語クラスにいるであろう他文化の人間との交流にも役立つはずだ。
もちろん、学習者の申し入れに対する配慮も考えたい。例えば、最初の授業では自分と同じ立場で立論させる。そのかわり、次の授業では反対の立場に立たせる。「自分で自分の意見を論破できるかな?」というのは面白そうで受け入れられやすいのではないか。
以上のとおり、今後このクラスでの活動を進めていきたいと考える。』
太字が今回追記した最後のまとめ(自説の再主張・問いへの再回答)です。
これを入れると確かにまとまりが良いですし、問いに応えていることがより明確になるのですが、なにせ字数が400字しかありませんから、スペースがなければ省略可、と考えます。
以上で記述問題対策は、終わります。
短い間でしたが、お付き合いありがとうございました。
勉強しすぎて失敗するパターン
とても大事なことを、ふと思い出したので追記させてください。
受験生の中には下記のような本を使って、多くの記述式問題を解いた方がおられると思います。 改訂版 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40
改訂版 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40
先に申しておきますと、この本について、賞賛したり、批判したりするわけではございません。
私が言いたいのは、
勉強しすぎると、その知識に引っ張られて本試験の記述問題で失敗する恐れがある
ということです。
旧司法試験では、10年以上受験を続けているベテランの方がたくさんいらしたのですが、
ベテランの方々が陥る罠がまさに、
勉強しすぎた知識に頼って論文を書いて自滅する
だったのです。
大学の講義でも経験ありませんか?
偉い学者さんの書いた基本書にもありませんか?
難しすぎて細かすぎて何言ってるか分からないや、
というものが。
全て同じ過ちを犯しています。
読み手(受け手)ではなく、自分中心で書いているのです。
知識がありすぎる状態で、本試験の記述問題に取り掛かると、
「ああ、この問題は前にも見たな。あれと同じように答案を書けばよいぞ」
「やった! これ予備校でやったやつとほぼ同じだ! 同じように書けば楽勝!」
などとつい考えてしまいます。
そのまま答案を書き始めると、失敗する可能性大。
なぜか?
問われていることが、微妙に異なっているからです。
例えば、
日本語クラスでディベートを取り入れるというテーマの記述問題でも、
「平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題17」
のような問い方と、
「日本で働きたい留学生に日本のビジネスマナーを理解してもらうため、ただ知識を教えるのではなく、日本のビジネスマナーの是非について、ディベート形式で議論してもらうのはどうか」
みたいな問い方では、
解答の書き方が、全然違いますよね?
ところが、知識に頼りすぎると、
「おっしゃ。以前やったディベートの話だ。同じように書けば余裕」
なんて考えて、失敗するのです。
私は22歳のときに旧司法試験に受かりました。合格者の平均年齢は約30歳です。
ベテランの受験生に比べて若く明らかに知識も経験も足りなかった私が生み出した論文対策が、
「問いに始まり、条文につなげ、あとは適当に書く」
というものでした(司法試験の論文試験では司法試験用六法が使えます)。
「問いの言葉」と「条文の言葉」で答案を埋めて、知識の足りなさをカバーするのです。
この書き方には、思わぬ利点がありました。
既有知識に頼らないので、ストレートに問いに対応できるのです。
日本語教育能力検定試験では六法が使えませんから、
「問いの言葉」しかありませんが。
知識に頼る前に、
問いに頼ってください。
問いに応えてください。
問題文の言葉をなるべく使ってください。
そうすれば、相手に伝わる答案が書けるはずです。
2023年度日本語教育能力検定試験記述が書けるようになる会
日本語教育能力検定試験の過去問には記述式問題解答例がついています。
ですがその解答例は専門家が時間をかけて書いたものです。
知識や前提条件が違いすぎてあまり参考になりません。
また、年度によって書き方が異なりパターン化できません。
そこで私は知識が少なくても合格答案が書ける方法を毎年お伝えしています。
結論を言います。
『問いに答える』ことです。
当たり前なのですが多くの人ができていません。
だから問いに答えるだけで合格できるのです。
・どうして問いに答えることができないのか。
・問いに答えるとはどういうことか。
今年も皆さんの答案を具体的に見ながらご説明していきます。
記述が書けるようになる会の詳細はこちら
全4回パック

第1回【9/10まで】

第2回【9/17まで】

第3回【9/24まで】

第4回【10/1まで】

記述が書けるようになる会に参加すると…
・ハマからの客観的な答案アドバイスを得られる。
・他の人の答案と自分の答案を見比べることで客観的な視点が持てる。
記述対策