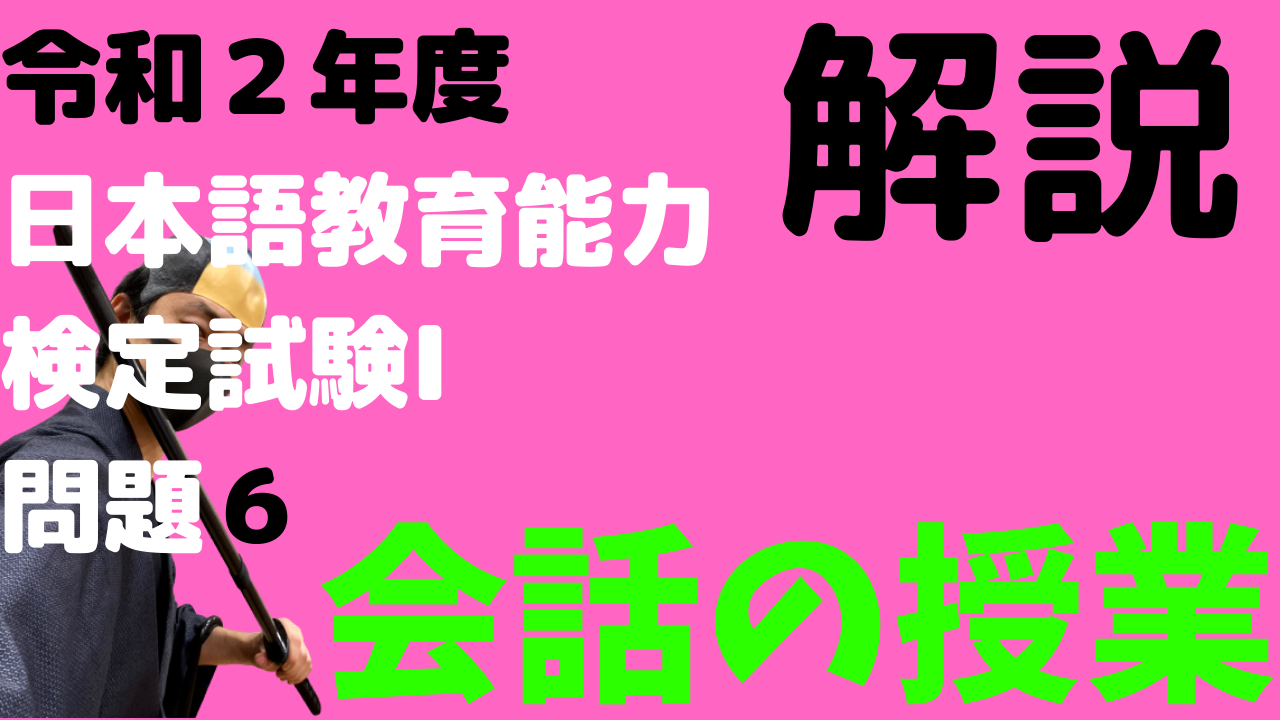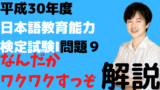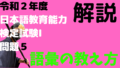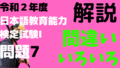令和2年度(2020年)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ問題6【コミュニケーション能力を高めることを重視した中級以上の会話の授業】の解説です。
問1 談話能力を高める指導の例
談話能力とは、どのように会話を始めて、どのように会話を進めて、どのように会話を終わらせるかという能力。
談話能力は、日本語教育能力検定試験の大好物ですから確実に理解しましょう。
直近では、令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1で、談話能力が欠如した例が問われています。
覚えていない方はこちらの動画を要チェック。
本文を見ると、社会言語能力などの言葉も出てきています。
談話能力、社会言語能力といえば、カナルの伝達能力(コミュニケーション能力)ですね。
伝達能力の4分類です。
| 文法能力 | 正しい語を使ったり、正しい発音をしたり、正しい表記をしたりする能力 |
| ストラテジー能力 (方略能力) | コミュニケーションを円滑に行うための能力。例えば、言葉が思い浮かばないときにジェスチャーで表現したり、相手の言葉がよくわからないときに表情を見て言いたいことを判断したり。 |
| 社会言語能力 | その場に応じた適切な表現を使う能力。例えば、客に対して敬語を用いたり。 |
| 談話能力 | 会話を構成する能力。会話を始めるときに「あのう」というフィラーを使ったり、相手に言ったことに対して適切な相槌をしたり、「では、そろそろ」など適切な表現で会話を終わらせたり。 |
選択肢1
例えば、「ひうまーく」というタイ人の方がいて、何を言っているかわからないときには、表情や体の動きを見ます。そこでお腹が減ってそうな表情やジェスチャーを読み取ることで会話が成立するかもしれません。
このように表現や体の動きなど非言語行動を意識して、コミュニケーションを円滑にしようとする能力は、ストラテジー能力です。
選択肢2
会話の相手(知らない人か友だちか)や会話の場面(フォーマルな場面かプライベートな場面か)に合わせた表現を考える能力は、社会言語能力です。
選択肢3
発音を正確にしようとする能力は、文法能力です。
選択肢4
談話能力とは、会話を構成する能力。会話を始めるときに「あのう」というフィラーを使ったり、相手に言ったことに対して適切な相槌をしたり、「では、そろそろ」など適切な表現で会話を終わらせたり。
A:すみません。
B:(Aさんの顔を見るだけ)
A:ちょっとよろしいですか。
B:(Aさん顔を見るだけ)
上のBさんは日本では適切なタイミングで相手の話を聞いていることをアピールするために、うなずいたり、「ええ」「はい」などの相づちが必要なことを知らなかったのでうまく会話を構成できていない。
会話を構成するというのは、切り出しから終わりまでの全て。
「あのうすみません」から「ありがとうございました」まで声の掛け方から会話の終わり方、相手へのあいづちなど会話をひとまとまりにまとめるためのもの。それが談話能力です。
よって、答えは4
問2 コミュニケーション・ストラテジーの例
コミュニケーション・ストラテジーとは、相手に言いたいことを伝えるため、あるいは相手の言いたいことを理解するための工夫です。
コミュニケーション・ストラテジーの例として不適当なものを選ぶ問題は、平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4で出題されています。
まだ、過去問を持っていない方は、買って確認してみてください。
過去問は試験直前になると売り切れることがありますので早めの入手をおすすめします。
すでに平成23年度から平成25年度は売り切れており、1万円近い値がついていることもあります。
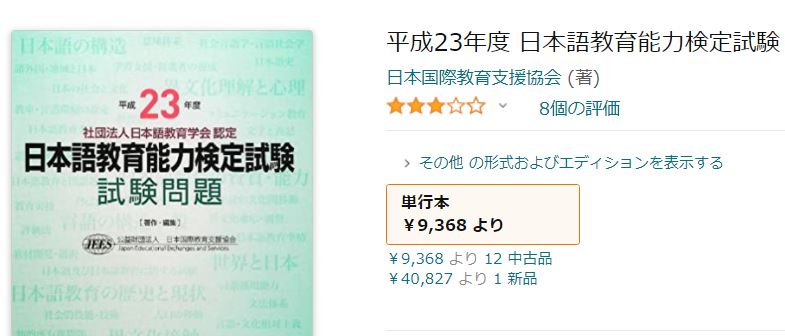
ストラテジー(工夫)といえば、他に学習ストラテジーがあります。
学習ストラテジー(言語学習ストラテジー)とは、勉強するための工夫です。
学習ストラテジーも毎年のように出題されていますので、確実に理解しておきましょう。
学習ストラテジーの種類についてはこちらの記事をご参照ください。
選択肢1
会話の中で新たに学んだ表現を忘れないようにメモをすることは、勉強のためなので学習ストラテジーです。
選択肢2
言いたいことが目標言語で言えない時に、母語を直訳して言うのは、相手に言いたいことを伝えるための工夫なので、コミュニケーション・ストラテジーです。
選択肢3
訂正された表現を繰り返すのは、コミュニケーションではなく、勉強のためなので学習ストラテジーです。
選択肢4
新しく習った表現を実際の会話の場面で積極的に使うことは、認知ストラテジーです。
よって、答えは2
問3 コミュ力養成を意識した書く活動
コミュニケーションとは、気持ちや意見などを相手に伝えること。
つまり相手が必要。
相手がいるかどうかという視点から各選択肢を見ていきましょう。
選択肢1
友人とコミュニケーションしてますね。
選択肢2
上司とコミュニケーションしてますね。
選択肢3
学食を考える人とコミュニケーションしてますね。
選択肢4
相手がいません。自己満足の妄想の世界です。
よって、答えは4
問4 プロフィシェンシーとは?
プロフィシェンシーといえば、プロフィシェンシーテスト、つまり熟達度テストが思い出されますね。
能力がどのぐらいかを見るテストのことです。
カタカナ語は元の言語の意味を調べると理解しやすいのでやってみてください。
Proficiency:熟達・技量
技量とは、物事を行うさま。腕前。
日本語教育においてプロフィシェンシーとは、日常生活の具体的な場面で、何かをお願いしたり、断ったりなどの課題を遂行する能力のこと。つまり技量ですね。
よって、答えは3
私は以前、プロフィシェンシーの育成を目指した本を読んだことがあったので、本試験でこの問題を見た時、「きたこれ!」とニヤニヤしました。
なかなか良い本だったのでよかったら見てみてください。
問5 語用論的転移の例
この問題はびっくりしました。
一年前の令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5を見てください。
文章中の下線部E「語用論的転移」の例として最もて適当なものを、次の1~4の中から一つ選べ
令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5
↑これ、令和二年の問題じゃないですよ。令和元年の問題です。
そう。一言一句同じ問が二年続けて出たんです!
さすがに選択肢は違いますが…。
このように日本語教育能力検定試験には好みがあり、大好物のキーワードは繰り返し出す傾向がありますので、過去問をしっかりやって日本語教育能力検定試験の大好物を把握しましょう。
語用論的転移とは、母語の社会文化的にはOKだけど、学習言語の社会文化的には誤りのもの。文法的には正しい。
選択肢1
文法的に正しくありません。
「できないとすると」を「できなければ」などに変えるべきです。
選択肢2
プレゼントをもらったときに「驚愕しました」をチョイスしたのが誤り。
母国の社会文化的影響は関係なく、単に選んだ言葉が不適切であると。
選択肢3
これは社会文化的な誤りですね。学習者の母国であれば、目上の人に対してもはっきり断っても問題ないのでしょう。
選択肢4
これは「正直に」という日本語が出てこなかったので「honesely」を使ったということで。
コミュニケーション・ストラテジーの母語使用です。
よって、答えは3
YouTube動画で過去問解説
関連する過去問
リンク先はYouTube解説動画あるいは解説ブログです。
・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1【談話能力が欠如した例】問5【語用論的転移】