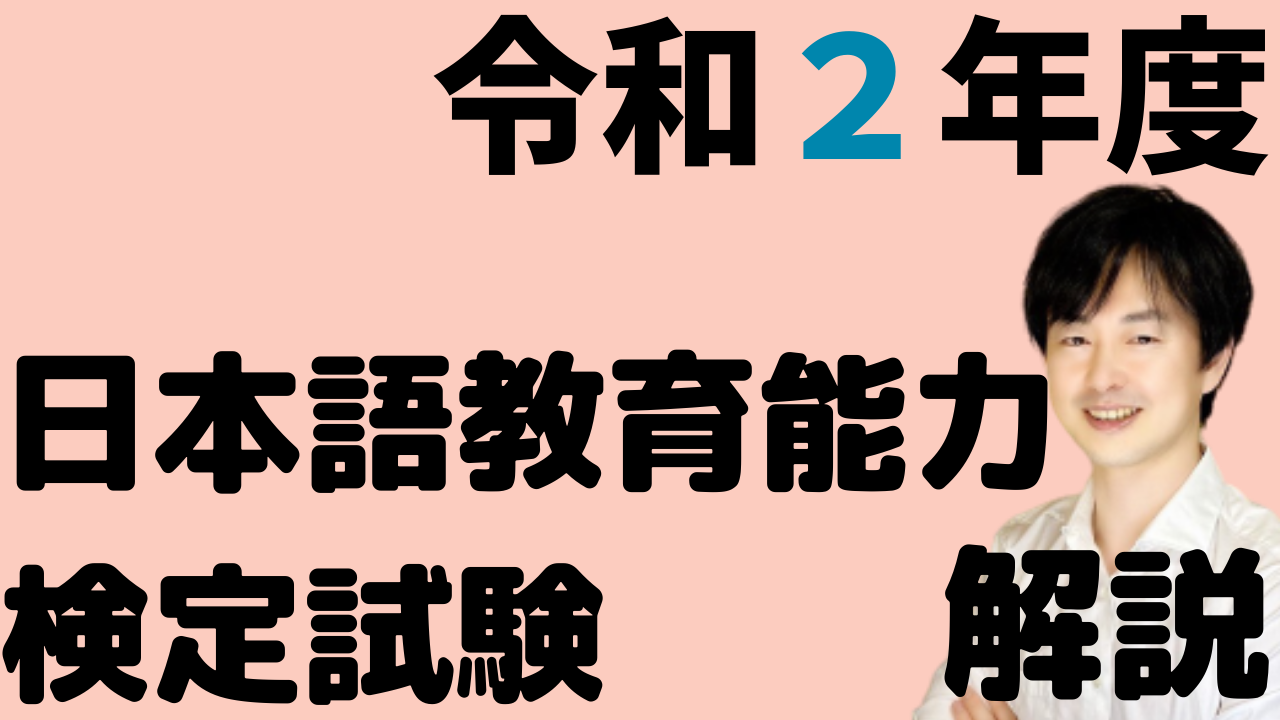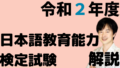令和2年度(2020年)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ問題9【臨界期仮説とバイリンガル教育】の解説です。
問1 臨界期仮説とは?
やってしまいました。
この問題は簡単です。臨界期仮説のことを知らなくても本文に説明がありますね。
1行目「ある年齢を過ぎると第二言語の習得が難しくなると言われている」
つまり、大人より子どもの方が習得しやすいということです。
ただし、語彙や文法が上級レベルになってくると、そもそも子どもの母語レベルでも足りなくなるので大人の方が有利になります。
例えば、JLPT(日本語能力試験)のN1は小学生には難しいでしょう。
と考えて本試験で選択肢3を選びました。
後日、解答速報を見てみると、
5校中4校が選択肢3を選んでいたので、
自信が確信に変わりました。
12月に発表された公式解答は4
確信は慢心でした。
よく考えたら
「ある年齢を過ぎると第二言語の習得が難しくなると言われている」からと言って、「大人より子どもの方が習得しやすい」とは限らないですね。大人の方が子どもより習得しやすいけど、ある年齢を過ぎた大人は習得が難しくなるということも考えられますから。
もう一度見直します。
臨界期仮説とは、ある年齢(学者によるが、例えば12,3歳ごろ)を過ぎたら、母語話者並の言語能力の習得は難しいという仮説
選択肢1
「自然習得が容易」なのは大人より子どもだろうと経験で判断できます。
私が小学2年生のとき、家族で大阪に引っ越しました。
私は学校1日目にして、家に帰ると大阪弁を使いだしたそうです。
選択肢2
これも明らかに違いますね。
この理屈が正しければ、2021年6月30日現在、世界最高齢の田中カ子(たなかかね)さん118歳が、最も第二言語習得に適した方ということになります。
選択肢3
大人と子どもの第二言語習得を比べると、学習のスピードや最終到達度に違いがあります。なんでも子どもがすぐれているわけではなく、学習の初期段階、特に形態素や統語に関しては、大人の方が速いといわれています。
小柳かおる著『第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと』p66より
選択肢は「大人」と「子ども」が逆です。
選択肢4
第二言語では、言語領域によって臨界期が異なるとも言われています。たとえば、発音に関する臨界期は早く、6歳とも言われています。でも、文法はもっと遅いと考えられています。
小柳かおる著『第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと』p66より
よって、答えは4
選択肢3も選択肢4も小柳かおる著『第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと』に書いてありました。Kindle版(電子書籍)があるのはありがたいです。
問2【バイリンガルの種類】バイリテラルとは?
バイリテラルとは、「聞く」「読む」も「話す」「書く」も二言語ともに十分に発達していること。
よって、答えは2
ほかに、4技能(「聞く」「読む」「話す」「書く」)の観点からバイリンガルを整理した場合、会話型バイリンガルと聴解型バイリンガルがあります。
詳しくは下の記事をどうぞ。
日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第4版だとp297、日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版だとp347に記載があります。
問3 認知的側面の構成要素とは?
学習言語は、言語的側面と認知的側面などから成るとする説がある、と言われると、
むむむ、
となりますが、その後にヒントがあります。
「その節目を説明する概念として、カミンズの学習言語能力(CALP)がある」
これです。
学習言語能力は生活言語能力よりも認知的な負担が大きくなるんでした。
「認知」という言葉は日本語教育能力検定試験によく出てきますので、理解しておいてください。
日本語教育能力検定試験で「認知」ときたら「頭を使ういろいろなこと」と言い換えれば大丈夫です。
例)認知能力→頭を使う能力
認知能力とは、知能検査で測れる能力。IQとか偏差値とか、脳を使ってするいろいろな能力。
例えば、日本人が英語で数学の授業を受ける場合、英語だけでも大変なのに、数学で頭を使うのでさらに大変になります。
学習言語の言語的側面とは、言語学習そのもの
学習言語の言語的側面の例)漢字や語彙を学習する。敬語の使い方を学習する。
学習言語の認知的側面とは、言語学習に付随する頭を使ういろいろなこと
学習言語の認知的側面の例)ドイツ語で書かれた医学書を読む際に必要になる医学の知識
選択肢1
「言語使用」と書かれていることからもわかりますね。「フォーマルな場面での言語の使い方」という言語そのものの学習なので、言語学習の言語的側面です。
選択肢2
「背景知識」は、言語学習そのものではなく、言語学習の際に役立つ背景知識なので、言語学習の認知的側面です。
選択肢3
「ノートを取ったり文章を要約したりする」のは、言語学習そのものではなく、言語学習を支えるスキルなので、言語学習の認知的側面です。
選択肢4
「著書の見方を理解して意図を探る」には、語彙を覚えたり文法を理解したりする言語学習そのものではなく、論理的に考えることが必要なので、言語学習の認知的側面です。
よって、答えは1
問4 生活言語能力と学習言語能力
カミンズの学習言語能力ときたら、セットで生活言語能力も覚えておきたいところです。
詳しくは下の記事を参照
学習言語能力は、「認知力必要度」が高く、「場面依存度」が低い言語活動ができます。
よって、答えは4
問5 二言語基底共有説とは?
この問題も難しかったですね。
解答速報では、2校が1、3校が3を選んでいます。
解答速報が割れるのは、できなくても大丈夫な問題です。
ですが、平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問4で類似の問題(母語と第二言語の言語能力は主に学習言語能力(CALP)を共有する)が出題されていますので、過去問をしっかりやっていたかたはできた問題かと。
カミンズの二言語基底共有説(氷山説)は、分離基底言語能力説(風船説)に対するものなのでセットで覚えておきたい。
分離基底言語能力説とは、風船説とも。
二言語基底共有説とは、氷山説とも。
選択肢1
二言語基底共有説(氷山説)では、氷山の下の見えない部分は二言語間で共有している、転移すると考えます。
何が転移するかは問3の選択肢が分かりやすいです。
問3の選択肢1のような「フォーマルな言語使用」というのは、英語と日本語で違いますから、転移しません。氷山の上です。
一方で、問3の選択肢2~4のような認知的側面、例えば「ノートを取ったり文章を要約したり」「著者の見方を理解して意図を探る」能力などは、英語でも日本語でも同じですね。
「数学等の概念知識」も日本語で勉強した数学の知識は、英語で数学するときも活かせますので、二言語間で転移します。
学習するときの工夫である「学習ストラテジー」も、二言語間で転移します。例えば、わからないことがあれば辞書で調べるという工夫は、日本語でも英語でもやります。
学習ストラテジーは毎年のように日本語教育能力検定試験で出題される最重要キーワードの1つですから、下記の記事で整理しました。読んでおいてください。
選択肢2
「2年程度で習得できる」「基本的な対話能力」というのは、生活言語能力のことでしょう。日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版353ページの表3-2-24参照。
選択肢3
「二言語を同等に使うためには、母語による認知能力の発達が必要」というのは、発達相互依存仮説のような考え方でしょうか。日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版353ページ参照。
二言語基底共有説というのは、「二言語を同等に使うため」の説ではなく、「二言語には共有している知識があるよね」という説です。
選択肢4
「二言語は独立して機能し、頭の中の限られたスペースで二つが共存している」というのは、風船説。日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版だと351ページの図3-2-4が分かりやすいので、見ておいてください。
よって、答えは1