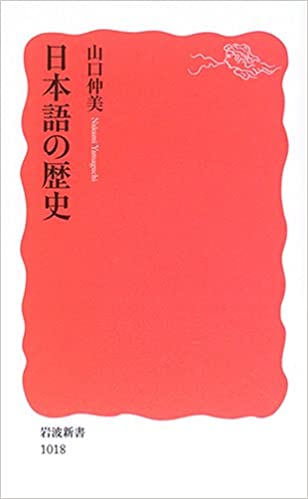平成30年度(2018)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ問題3Dは【日本語の歴史】です。
過去問解説(16)中世を境に
解き方
問題文にヒントがあります。「中世を境とした」
中世より前が(ア)
中世より後が(イ)
選択肢から中世より前っぽい言葉を探すと「古代」 中世より後っぽい言葉を探すと「近代」
よって、答えは4です。
各用語の意味
古代語とは、日本語の歴史を中世を境に二分した時の中世以前の言葉
近代語とは、日本語の歴史を中世を境に二分した時の中世以降の言葉
口語とは、話し言葉
文語とは、書き言葉
上方語とは、上方(京都・大阪)で使われる言葉。特に江戸時代のもの。
江戸語とは、江戸時代に江戸で使われていた言葉
古語とは、昔使われた言葉で現代では使わない言葉
新語とは、新しく作られたもの、使われるようになった言葉
例)草生える(面白いという意味)
過去問解説(17)一段化
解き方
「二段動詞の一段化」と言っているので、五段動詞「折る」の選択肢3,4は除外。選択肢1と2を比べてどちらが自然な変化の流れか。2は3文字→2文字→3文字になっていて変。1のほうがナチュラルな変化。よって答えは1。古文の知識がなくても解ける問題です。
二段動詞とは、動詞を活用するときに活用語尾が二段になる動詞。
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 | ||
| 古語 | 食べず | 食べつ | 食ぶ | 食ぶること | 食ぶれば | 食べよ | 下二段活用 |
| 現代語 | 食べない | 食べます | 食べる | 食べること | 食べれば | 食べろ | 下一段活用 |
古語では、活用語尾が「べ(エ段)」と「ぶ(ウ段)」の二段ですね。また、終止形は「食ぶ」、連体形は「食ぶる」と形が違いますが、現代語では、終止形と連体形のどちらも「食べる」ですね。これが終止形と連体形の合流です。
動詞のグループの見分け方
動詞のグループを見分けるときは「ない」をつけてみるのがオススメ。五段動詞は「ない」の前がア段になります。
折らない
一段動詞は「ない」の前がイ段(上一段)かエ段(下一段)になります。
食べない。
過去問解説(18)係助詞
係助詞ってはるか昔に古文の授業で勉強したけど覚えてない…という人も大丈夫! 現代文の助詞の知識があれば解けます! この問題に関しては問題文に惑わされず、選択肢だけ見た方がいいですね。
解き方
- 「か」は並立助詞です。「猫か犬」
- 「も」は取り立て助詞です。「あの猫も好きです(他の猫も好き)」
- 「は」は取り立て助詞です。「猫は好きです(犬はちょっと…)」
- 「ぞ」は終助詞です。「猫カフェに行くぞ!」
よって、答えは2です。
係助詞の意味と種類
せっかくなので関連知識を勉強しましょう。
助詞とは、他の語を助ける詞(ことば)、つまり単独では使えない。形の変化もない。
係助詞(かかりじょし)とは、強調したり、疑問を表すために使う助詞。係助詞を使う時は文末の活用語の形が決まっている(係り結び)。
例)もと光る竹なむ一筋ありける。
本来は「もと光る竹、一筋ありけり」ですが、係助詞の「なむ」が入ったため、「けり」→「ける」に変化。
係助詞には、「か・も・は・ぞ・なむ・や・こそ」の7つがある。
助詞の種類と意味
接続助詞とは、前後の節を接続する。つなげる。
例)猫なのに納豆を食べる。
取り立て助詞とは、文面に書いてない情報を取ってきて立てる助詞。情報を付加する助詞。
例)サッカーも好きです。
取り立て助詞「も」を使うことで、サッカー以外も好きなものがあるという情報が付加されている。
格助詞とは、名詞について名詞と述語の関係を示す。
例)猫と遊ぶ(猫は遊び相手という関係)
並立助詞とは、並べて立たせる助詞。つまり対等な関係で列挙する。
例)猫と犬、猫か犬
終助詞とは、文の終わりについて、話し手の気持ちなどを表す。
例)今年は雨が多いですね。
過去問解説(19)「くれる」と「やる」
「くれる」と「やる」は何が対立しているのか。各選択肢を見る。
1.動作性
「くれる」と「やる」はどちらも動作性があるので対立していない。
動作性に関わる対立の例)「する」と「できる」
2.視点
「くれる」は外→内。マドンナが(私に)チョコをくれた。
「やる」は内→外。(私は)マドンナにチョコをあげた。
視点が対立しています。
3.相
相(そう)とは、アスペクトの日本語訳。
アスペクトとは、その動作(出来事)のどの段階を切り取るか。アスペクトといえば「ている」
例)食べている。
食べるという行為が継続している段階。
「くれる」と「やる」にアスペクトの対立はないですね。
アスペクトに関わる対立の例)「食べる」と「食べている」
4.時制
時制と行えば、現在、未来、過去。
「くれる」と「やる」に時制の対立はないですね。
時制に関わる対立の例)「食べる」と「食べた」
よって、答えは2です。
過去問解説(20)日本語の変化
解き方
これは知識がなくてもロジックで解ける問題です。各選択肢は日本語の変化について書かれていて、それを「日本語内部における変化」と「外国語の影響による変化」にわけることができればよし。やってみましょう。
1.敬語が相対敬語に。
外国語の影響で相対敬語になるだろうか? ちょっと考えられない。韓国は絶対敬語だしなあ。日本内部における変化っぽい。
2.ラ行音で始まる単語の使用
使う単語が増える理由の一つは外来語だ。特に今まであまりなかったタイプの単語(ラ行音で始まる単語)が増えるのは、それが元々日本にはない言葉だからだろう。つまり外国からの影響なので「内部」じゃない。
3.閉音節構造の単語の使用
今までになかったタイプの単語(閉音節構造の単語)を使うのは元が外国の言葉、外来語だからだろう。「内部」じゃない。
4.漢語の使用
漢語は中国から。「内部」じゃない。
よって、答えは1です。
用語の意味
絶対敬語とは、絶対に敬語です。年上など敬語を使う相手には、状況や場面に関係なく敬語。韓国語の敬語。昔の日本。
相対敬語とは、相対に敬語です。状況や場面で変わります。例えば部長と話すときは部長の行為に尊敬語を使いますが、外のお客さんと話すときは部長の行為に謙譲語を使います。今の日本語の敬語。
例)部長に対し尊敬語「部長はいらっしゃいますか」
お客さんに対し謙譲語「部長の浜は、まもなく参ります」
開音節とは、母音で終わること。日本語はこれ。スペイン語も開音節なので日本人にとって英語より発音しやすい。
閉音節とは、子音で終わること。英語、中国語、韓国語など。
日本語にも「ん(n)」で終わる単語など閉音節がありますし、英語にもdata[deɪtə]など開音節があります。