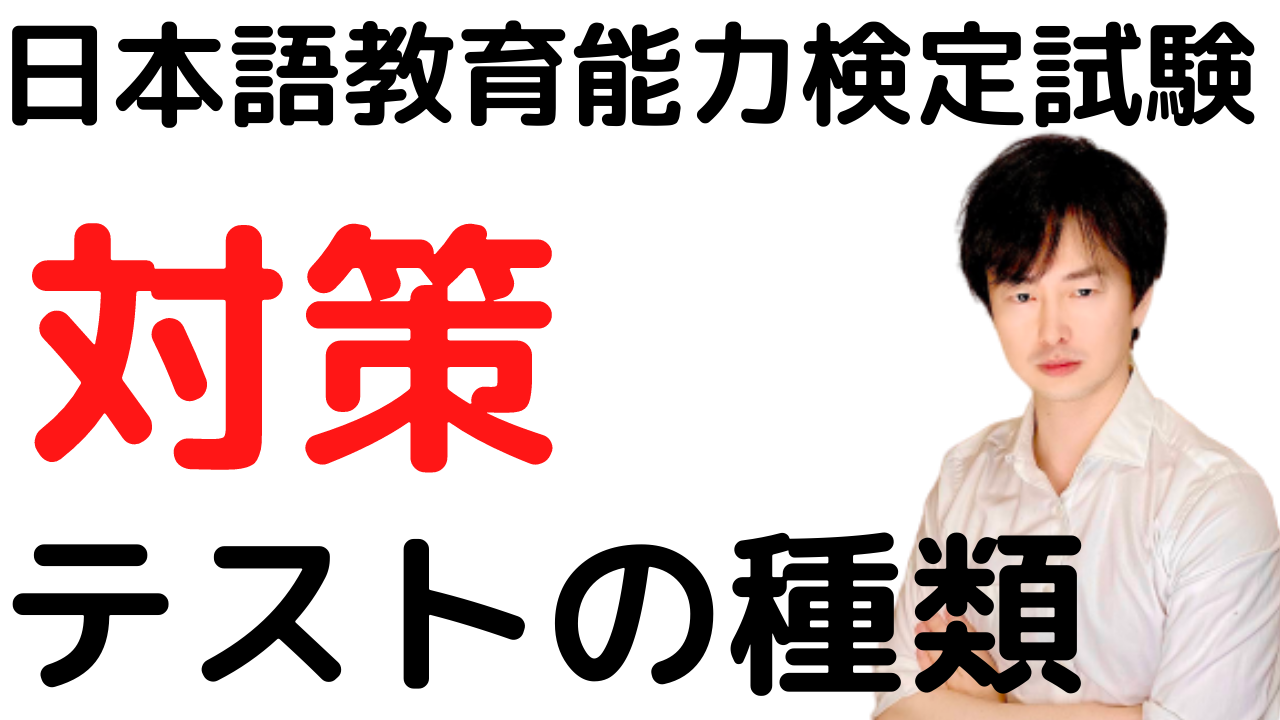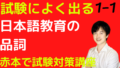テストの種類【採点方法で分類】
客観テストとは?
客観テストとは、正解が客観的に1つしかないテスト。答えが客観的に1つに絞れるテスト。だれが採点しても同じ。コンピューターも採点できる。
例:選択式、○×式など
再認形式と再生形式の2種類があります。勉強したことを思い出してテストに再現するので「再」という言葉を使っています。
客観テスト(例:選択式、○×式など)の利点
採点の公平性と一貫性
- 明確な正答があり、採点者によるばらつきがない。
短時間で多数を評価可能
- 自動採点が可能で、時間と労力の節約につながる。
統計的な分析がしやすい
- 点数や分布をデータとして扱いやすく、学力の比較や分析に向いている。
出題範囲が広く取れる
- 多くの問題を出せるため、学習範囲全体の理解度を幅広く測定可能。
客観テストの作成形式【再生形式】
再生形式とは、受験者が自分で答えを書く形式。
| 再生形式のテスト | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 単純再生法 | 単純な質問 例)日本語教育能力検定試験はいつか? | |
| 訂正法 | 誤りを見つけて直す。 例)昨日、猫カフェに行きます。 →答え:行きました。 | |
| 完成法 | 未完の文を完成させる 例)昨日、猫カフェに( )。 →答え:行きました。 | |
| 質問法 | 長文を読んだ後に内容についての質問に答える。 | 次の文章を読み、下の問いに答えよ。 (文は省略) 1.太郎はどうして新幹線に乗らなかったのか。 |
| クローズ・テスト (クロース法) | 文章に一定間隔で設けられた空欄を適切な文字や語で埋める (平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問4) | 私は昨日、サイゼリヤに( )ました。サイゼリヤはとてもやす( )、おいしかったです。また行き( )です。 |
客観テストの作成形式【再認形式】
再認形式とは、書かれてある答えを選ぶ形式。
| 真偽法 | 〇× 例)正しいものには〇、正しくないものには×を書きなさい。 |
| 多肢選択法 | 複数の選択肢から正答を選ばせる。 例)センター試験、日本語教育能力検定試験 |
| 組み合わせ法 | 複数のものから組み合わせをつくる。 例)続く言葉を線で結べ 1.昨日は学校に・ ・食べました。 2.昨日はバナナを・ ・行きました。 |
| 再配列法(並べ替え) | 正しい語順に並び替える。 例)正しい文になるよう並び替えよ。 |
客観テストの例
・JLPT
・記述問題を除く日本語教育能力検定試験
主観テストとは?
主観テストとは、1つの決まった答えはなく、採点基準に基づいて、点数をつけるテスト
例:記述式、論述、面接など
主観テスト(例:記述式、論述、面接など)の利点
思考力・表現力を評価できる
- 単なる知識の有無だけでなく、論理的思考・創造性・意見の形成力などを測定できる。
理解の深さを把握できる
- 曖昧な知識や誤解を含む解答も拾い上げて、学習の本質的な理解度を見極めやすい。
自由な表現が可能
- 受験者の独自の視点や考え方、文章構成力などを評価対象にできる。
言語運用能力の測定に適する
- 語学教育などでは、記述や発話などの主観的なテストでしか測れない力がある。
主観テストの例
・プレゼン
・面接
・日本語教育能力検定試験の記述問題
| NRT | CRT | |
|---|---|---|
| 実施目的 | 集団の中でその受験者がどのレベルにいるか | その受験者がどこまでできるか。 |
| 評価 | 相対評価 | 絶対評価 |
テストの種類【実施目的で分類】
集団基準準拠テスト(NRT)とは?
集団基準準拠テストとは、集団の中である個人がどの位置にいるか測るテスト。他の人と比べる。相対評価。
NRTは【Norm Referenced Test】の略
平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問2では【集団基準準拠テストに関する記述として不適当なものは?】が出題されました。
集団基準準拠テストの特徴
・受験者間の能力の違いを明らかにすることができる。
・個人の結果を解釈するときに、平均値や標準偏差などを用いて、他の人と比べる。
・得点分布を見ることで、できない人とできる人の差が大きいとか、中間層が多いとか、受験者の特徴を理解することができる。
(以上は平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問2より)
・結果は集団中で自分がどの位置にいるか知るために使う。
・他の受験者と比較するために、全受験者のテスト内容は同一でなければならない。
・他の受験者との差を見るために、弁別力が高くなければならない。
※弁別力とは、違いを区別しやすいこと。テストでは、高得点の人が正解できて、低得点の人が正解できない問題を弁別力が高いという。
集団基準準拠テストの例
・入学試験
・プレースメントテスト(クラス分けテスト)
目標基準準拠テスト(CRT)とは?
目標基準準拠テストとは、ある受験者のできること(Can-do)や、能力の伸びを明らかにするテスト。目標に対する個人の到達度を測ることが目的。個人が何をできるか。どこまでできるか。どこまでできるようになったか。絶対評価。CRTとも。
CRTは【Criterion Referenced Test】の略
目標基準準拠テストの特徴
・目標に対する個人の到達度を測ることが目的(平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問2)
・個人が一定のレベルを満たしているか確認することが目的
・コースの途中や終わりに、学習者が学習内容をどこまで習得したか確認するのに使う。
・結果は、学習や指導の改善のために使う。
・個人ごとに異なるテスト内容にすることで、より細かい達成度を知ることができる。
目標基準準拠テストの例
・アチーブメント・テスト(到達度テスト)
・期末テスト
テストの種類【用途で分類】
適性テスト(アプティテュード・テスト)とは?
適性テストとは、受験者が語学学習に適性があるかどうか測るためのテスト。アプティテュード・テストとも。現代言語適性テストと外国語学習適性テストがある。
現代言語適性テスト(MLAT)とは?
現代言語適性テストとは、一般成人向けに作られた言語適性を測るテスト。MLATとも。
第二次世界大戦時の英米で、短期間で外国語を習得できる人材を選抜するための言語適性テストを開発。戦後、キャロルらが言語適性テストを一般化したのがMLAT
MLATは【Modern Language AptitudeTest】の略
現代言語適性テストでは、以下の4つの学習能力をチェックすることで、言語適性を見る。
①音声と文字を一致させる力
②文法に対する敏感さ
③機械的な記憶力
④帰納的に理解する力
外国語学習適性テスト(PLAB)とは?
外国語学習適性テストとは、学校教育の現場で使用するために作られた言語適性を測るテスト。PLAB、ピムスルール言語適性バッテリーとも。
PLABは【Pimsleur Language Aptitude Battery】の略
外国語学習適性テストでは、①言語的知性②音韻的能力③分析能力を測る。
組み分けテスト(プレースメント・テスト)とは?
組分けテストとは、学習者の現在の実力を測り、適正なクラスへ配属するためのテスト。プレースメント・テストとも。
到達度テスト(アチーブメント・テスト)
到達度テストとは、一定期間における学習の到達度を見るためのテスト。アチーブメント・テストとも。
熟達度テスト(プロフィシエンシー・テスト)
熟達度テストとは、受験者の能力が認定基準に照らしてどのレベルかを測るためのテスト。プロフィシエンシー・テストとも。
よいテストの条件
| 妥当性 | テストで測ろうとしているものが測れているか |
| 信頼性 | 受験者が真の実力を見せれくれるテストか |
| 客観性 | 別の人が採点しても同じような結果になるか |
| 有用性(実用性) | 使いやすいか |
| 真正性 (オーセンティシティ) | 受験者の実際の言語使用の状況を反映しているか |
妥当性と信頼性の違いについて詳しくは下の記事をどうぞ
テストの種類が出題された日本語教育能力検定試験の過去問
・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16
・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15【日本語のテスト】
・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問1【熟達度評価として行われるテストは?】問2【訂正法と呼ばれるテスト形式の例】問3【テストの妥当性を損なう要因】問4【標準偏差の説明】
・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問4【読解能力を測定する方法としても活用できるクローズテストの説明】
・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問2【集団基準準拠テストに関する記述】問3【テストの妥当性に関する記述】