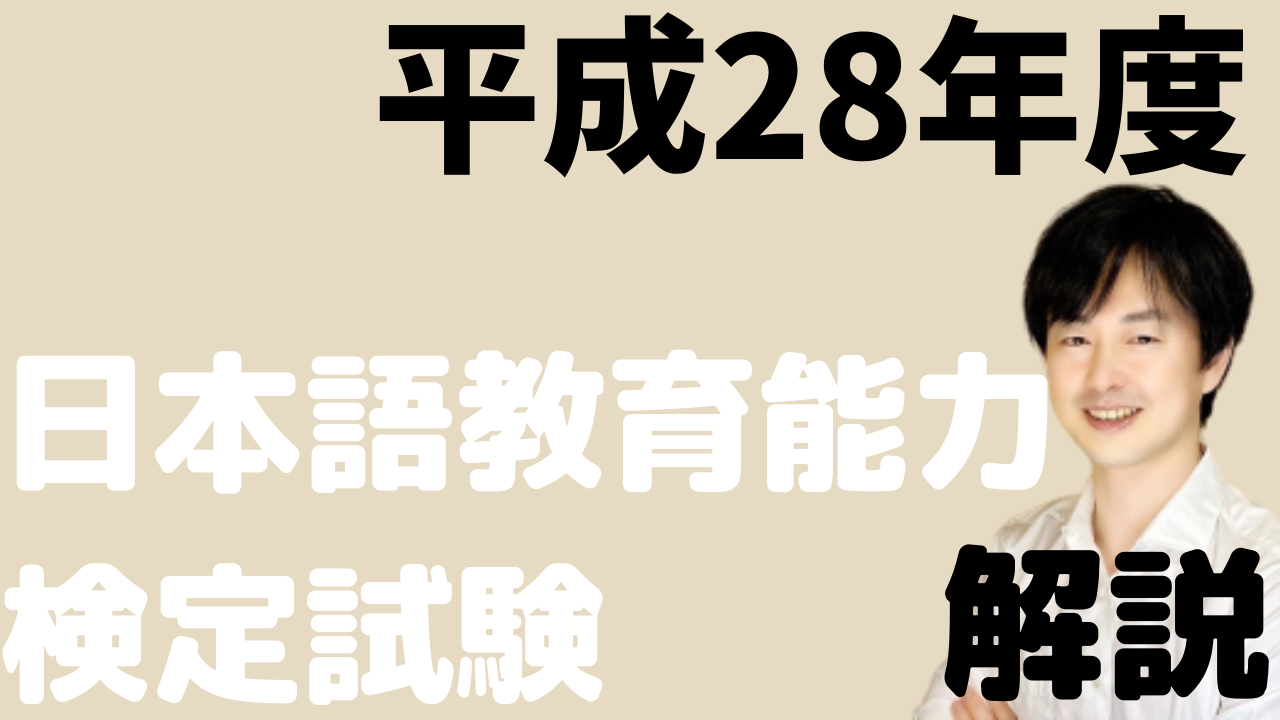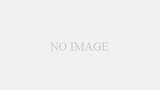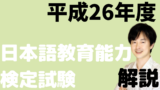問1の解き方
選択肢1
理解優先、発言はしなくていいよー。
これはナチュラルアプローチやコンプリヘンション・アプローチのことかと。
選択肢2
「習慣」「母語の干渉をなくす」ときたら、オーディオ・リンガル・メソッドです。
選択肢3
これは帰納的アプローチですね。帰納的な文法指導については令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2で問われたように「多くの目標言語の実例に接してから、そこに現れた文法規則を発見」させます。
帰納的アプローチについては平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1でも出題されていますので要チェックです。
選択肢4
「意味交渉」で「言語習得が促進」と来れば、コミュニカティブ・アプローチです。
よって、答えは4
問2の解き方
1 対話の相手から否定証拠が与えられること
現実のコミュニケーション場面では「否定証拠」は与えられにくいです。
×
よって答えは1
2 発話者に情報の選択権があること
現実のコミュニケーション場面では、発話者に情報の選択権があります。
〇
3 対話者間に情報の格差があること
現実のコミュニケーション場面では、対話者間に情報の格差があります。
〇
4 対話者間のやり取りに真正性があること
現実の使用場面のような言語活動を行うには真正性が保たれている必要があります。
よって、答えは1
問3の解き方
問題文に「タスク(課題)を達成することを主眼とした」という大ヒントがあるので落としたくない問題です。
選択肢1
「日本語のレシピを見ながら、カレーライスを協力して作る」というタスクを達成することを主眼としています。
選択肢2
「就職活動で必要になるエントリーシートや履歴書を作成する」というタスクを達成することを主眼としています。
選択肢3
「住んでいる町を紹介するパンフレットを分担して作る」というタスクを達成することを主眼としています。
選択肢4
パターン・プラクティスは文型練習です。タスクではありません。
よって、答えは4
問4の解き方
コミュニケーション・ストラテジーについては下の記事をどうぞ。
選択肢1
「言語上の問題が起こったら、話題を違うものに変える」のは、コミュニケーション・ストラテジーの話題転換です。
選択肢2
難しい言語形式の使用を避けたり、言いたい内容を省略したりするのは、コミュニケーション・ストラテジーの回避です。
選択肢3
母語を直訳したり、母語の語彙をそのまま使ったりするのは、コミュニケーション・ストラテジーの母語使用です。
選択肢4
言語上の問題が起こっても、気にしないように自分を励ますのは、情緒や態度をコントロールすることなので、言語学習ストラテジーの情意ストラテジーです。
よって、答えは4
問5の解き方
内容言語統合型学習(CLIL)については下の記事をどうぞ
選択肢1
「教科内容の知識と言語能力の獲得を目指し、複数教科の学習を目標言語で行う」のは、CBI(Content-Based Instruction)のことでしょうか。
CBI は教科内容を外国語で行うことを提唱した教育法であり(Snow, Met, & Genesee, 1989), 学習者は, 教科学習を通して外国語に触れ, 何が言われてい るのか, または書かれているのかに関心を持ち, そのメッセージの内容を理解しようと試み, それに対して自分の意見を述べる。 この過程を通して外国語を習得すると考えられている。
内容を重視した外国語教授法―CBI と CLIL―
選択肢2
CLILといえば、「内容(Content)」「言語(Communication)」「思考(Cognition)」「協学(Community)」です。
〇
選択肢3
「目標言語での学習活動において、生活言語能力の伸長を促す」ことを主張している学習法はあるのでしょうか? 私は知りません。ご存知の方、ご教示いただけると幸いです。
選択肢4
「教室では目標言語だけを用い、音声中心で言葉の意味を理解させ習得を促す」のは直接法のことでしょうか。直接法は令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2で問われていますのでそちらも要チェック!
よって、答えは2
以下は日本語教師になる前に書いた解説です。
※他の解き方、考え方を知るのに役立つので、あえて残しています。
日本語教育能力検定試験では、ほぼ毎年試験Ⅰの問題4で、教授法に関する問題が登場しますので、教授法は最重要分野の一つ。過去の問題4もチェックして今年の問題4に備えましょう。
2016日本語教育能力検定試験Ⅰの問題4は、コミュニケーション能力の育成を重視した教授理念です。この記事ではコミュニカティブ・アプローチ、タスク中心の教授法について学びます。
問1 コミュニカティブ・アプローチの背景となる考え方とは?
コミュニカティブ・アプローチがコミュニケーション能力の育成を重視するのは
会話の中で意味交渉が生じることによって
言語習得が促進されると考えるからです。
よって、正解は4です。
意味交渉については下記の記事参照
問2 コミュニカティブ・アプローチによる言語活動を行う際に必要とされる条件とは?
コミュニカティブアプローチでは、現実のコミュニケーションと同じような条件を必要とします。
すなわち、発話者に情報の選択権があること(チョイス)
対話者間に情報の格差があること(ギャップ)
対話者間のやり取りに真正性があることが必要です。
現実のコミュニケーションに否定証拠は多くありませんので、対話の相手から否定証拠を与えられることは必要とされる条件ではありません。
よって、正解は1です。
否定証拠については平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5を見てください。
問3 「タスク中心の教授法」に基づく学習活動とは?
タスク(課題)を達成することを主眼としたタスク中心の教授法は、コミュニカティブ・アプローチの考え方が基盤になっています。タスク中心の教授法に基づく学習活動として不適当なものを選びます。
1,日常語のレシピを見ながら、カレーライスを作るというタスクを達成することが目的。
2,就職活動で必要になるエントリーシートや履歴書を作成するというタスクを達成することが目的。
3,住んでいる町を紹介するパンフレットを分担してつくるというタスクを達成することが目的。
4,パターン・プラクティスといえば、コミュニカティブ・アプローチの天敵、オーティオリンガルメソッドの練習法です。
よって、正解は4です。
問4 コミュニケーション・ストラテジーの例
平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4を検討します。学習者が言語上の問題を切り抜けようとして用いるコミュニケーション・ストラテジーの例として不適当なものを選びます。
1,言語上の問題が起こったら、話題を違うものに変えるのは、コミュニケーションストラテジーの話題転換です。
2,難しい言語形式の使用を避けたり、言いたい内容を省略したりするのは、コミュニケーションストラテジーの回避です。
3,母語を直訳したり、母語の語彙をそのまま使ったりするのは、コミュニケーションストラテジーの言語交換です。
4,言語上の問題が起こっても、気にしないように自分を励ますのは、情緒や態度をコントロールすることなので、情意ストラテジーです。
よって、正解は4です。
コミュニケーションストラテジーをもっと知りたい方に下の記事をプレゼント
問5 内容言語統合型学習(CLIL)
CLIL(内容言語統合型学習)は、教科内容を題材とし、内容・言語・思考・協学を結びつけた指導を行います。
よって、正解は2です。