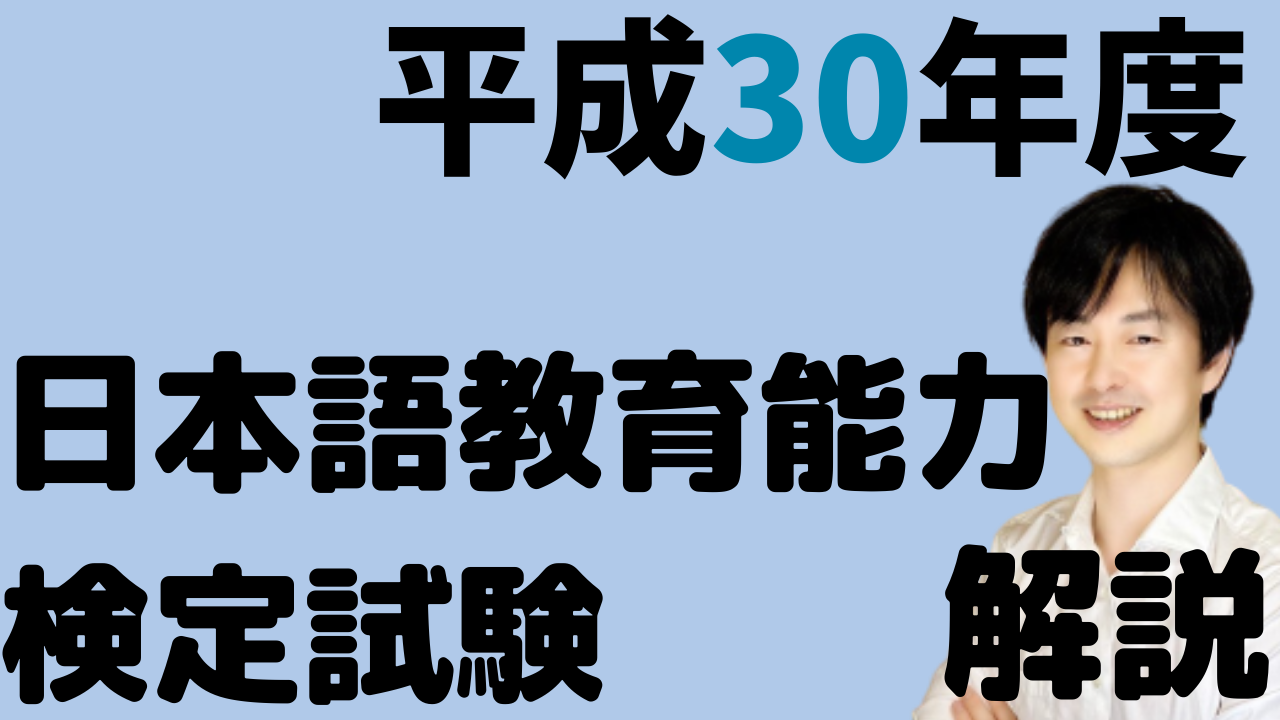問1の解き方【モニターモデル】
クラッシェンのモニターモデルについては下記の記事をどうぞ
選択肢1
モニターの役割を果たすのは「学習によって」得られた知識です。
×
選択肢2
そのとおりです。
〇
選択肢3
「目標言語による相互交流はインプットの理解を促すので習得を促進する」と考えるのはインターアクション仮説です。
×
選択肢4
「未修の語彙や表現が内容調整したインプット」ではなく
自分の言語能力よりちょっと高いレベルのインプットが習得を促進すると考えます。
なので未修の語彙や表現がちょっとあります。
×
よって、答えは2
問2の解き方【ナチュラル・アプローチ】
ナチュラル・アプローチの説明はこちら
選択肢1
「ロッド」といえばサイレントウェイです。
サイレントウェイでは、教師はロッドを使い、学習者が既習の知識を基に規則を類推するよう働きかけます。
×
選択肢2
ナチュラル・アプローチでは、教師は学習者の不安の軽減に努めるため、学習者に話さようとしません。
「話さなくていいんだよ。聞くだけでいいんだよ。気楽でしょ?」
これがナチュラル・アプローチです。
×
選択肢3
「習慣形成」といえば、オーディオ・リンガル・メソッドです。
×
選択肢4
「理解可能な言語インプットを大量に与えることで、言語能力の習得」ができると考えるのはナチュラル・アプローチの理論的基盤であるモニターモデル(インプット仮説)です。
〇
よって、答えは4
問3の解き方【社会言語能力】
社会言語能力や各選択肢の能力についてはこちら
選択肢1
「文化や場面に適切な言語・非言語表現を選んでコミュニケーションできる能力」は社会言語能力です。
選択肢2
「会話が文章に置いて結束性・一貫性のある意味のまとまりを形成する能力」は談話能力です。
選択肢3
「語彙、形態素や統語の知識、文レベルの意味的側面、音韻規則を扱う能力」は文法能力です。
選択肢4
「コミュニケーションが滞った場合、言い換えなどにより会話を維持する能力」は方略能力です。
よって、答えは1
問4の解き方【理解可能なアウトプット】
ぎゃー
カタカナだらけ! 知らない言葉だらけ!
こういうときのテクニックがあります。
聞いたことがない言葉は不適当
聞いたことがある言葉は適当
と考えます。
聞いたことがある言葉→勉強している、過去問に出てきた→関係ある可能性が高い(適当)
聞いたことがない言葉→勉強していない、過去問に出ていない→関係ない可能性が高い(不適当)
という理屈です。
選択肢を見てみると、
聞いたあるのは選択肢2「インフォメーション・ギャップ」だけ。
よって、答えは2
日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版の後ろの索引から各選択肢の言葉を探してもあるのは「インフォメーション・ギャップ」だけです。
選択肢1
プロセシング・インストラクションは、インプット重視の指導法です。アウトプットを引き出す授業活動例ではありません
英語では、Processing Instruction。略してPI
Processing Instructionというのは、新しいターゲットとなる文法と、もう1つ以前習った既習の文法事項を対比させながら、両方の文法に気づかせて定着をはかっていこうという指導法です。
https://jlc-eteaching.jimdo.com/series-kyoto-ufs-e139a/
詳しくは、「Processing Instruction(処理指導)の 効果に関する研究」をどうぞ。
選択肢2
インフォメーション・ギャップ・タスクとは、情報差のあるタスク(課題)のこと。
インフォメーション・ギャップ・タスクの例
例えば「相手をディズニーランドに誘う」というタスクです。
A:「Bさん、今度ディズニーランドに行きませんか」
B:「いいですよ」
A:「明日はどうですか」
B:「すみません、明日はちょっと」
A:「じゃあ、明後日は」
B:「明後日は大丈夫です」
A:「じゃあ明後日に!」
Aさんは、Bさんがいつ空いているか知りません。ここにインフォメーションギャップがあります。
なのでAさんはBさんに「いつが空いているか」聞かなければなりません。
Bさんが答えるには「相手が理解可能なアウトプット」をしなければなりません。
例えばタイ語を知らないBさんにタイ語で「เมื่อไหร่จะว่าง」と聞いても、
Bさんは理解できず、Bさんをディズニーランドに誘うことができません。
インフォメーション・ギャップ・タスクは、「理解可能なアウトプット」を引き出すことのできる授業活動です。
〇
選択肢3
パラレル・リーディングとは、音声を聞きながら同時に声に出して読んでいくこと。オーバーラッピングとも。
聞いている言葉、読んでいる言葉をそのまま声に出すだけなので、アウトプットとは言えません。アウトプットとは自分の中(脳内)にあるものを外に出すことです。
選択肢4
サイト・トランスレーションとは、前から順に、意味のかたまりごとに訳していくこと。
英語は、Sight Translation
Sight(サイト)は「一見(ちょっと見ること)」
Translation(トランスレーション) は「訳すこと」
つまり、サイトトランスレーションとは「見てすぐ訳す」と言う意味
サイト・トランスレーションは通訳者や翻訳者になるための勉強法です。
例えば、アメリカ人に対する日本語の授業でサイト・トランスレーションを行うとすれば、
日本語を英語に訳してもらうあるいは英語を日本語に訳してもらうことが考えられます。
理解可能なアウトプットとは、相手に理解してもらえるようなアウトプットのことです。
日本語→英語に訳す:相手はアメリカ人なので当然理解しますが、相手にとっては日本語の勉強になりません。
英語→日本語に訳す:文をそのまま訳すので、相手に理解してもらえるかどうかの配慮はありません。
よって、答えは2
問5の解き方【日本語指導が必要な外国人児童生徒等】
「日本語指導が必要な外国人児童生徒等」に対する文部科学省の教育施策といえば「CLARINET(クラリネット)です」
日本語指導が必要な児童生徒はよく出題されますので、 CLARINETを見ておいてください。
選択肢1
JSLカリキュラムは、外国人児童生徒が学校での学習や生活に円滑に適応できるようにするため、日本語指導の初期学習から教科学習につながる段階までをカバーするものとして、平成13年度より研究開発を進めてきました。(中略)
多様な背景を持つ外国人生徒が「日本語で学ぶ力」を確実に身に付けることができるよう、学校における授業づくりを支援するための様々な配慮を盛り込み、作成しました。(中略)
関係者の皆様におかれましては、JSLカリキュラムを授業実践や研修の指導資料等としてご活用していただき、外国人児童生徒への日本語指導の一層の充実を図っていただきたいと考えております。
学校教育におけるJSLカリキュラム(中学校編)
上記黄色ハイライトの通り、JSLカリキュラムは「日本語で学ぶ力」を身に付けることが目的です。
「継承語の保持のために母語による学習支援を強調」していません
×
選択肢2
「日本語指導者等に対する日本語指導の研修が国際交流基金で行われている」
その通りですが、国際交流基金は文部科学省ではありません。
×
選択肢3
児童生徒の在籍する学校における「取り出し指導」を原則とする。ただし、指導者の確保が困難な場合には、他校における指導も認める。
日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施について(概要)
そのとおりです。
〇
選択肢4
DLAについてはこちら。「筆記テスト」ではなく対話型の評価方法です。
×
よって、答えは3