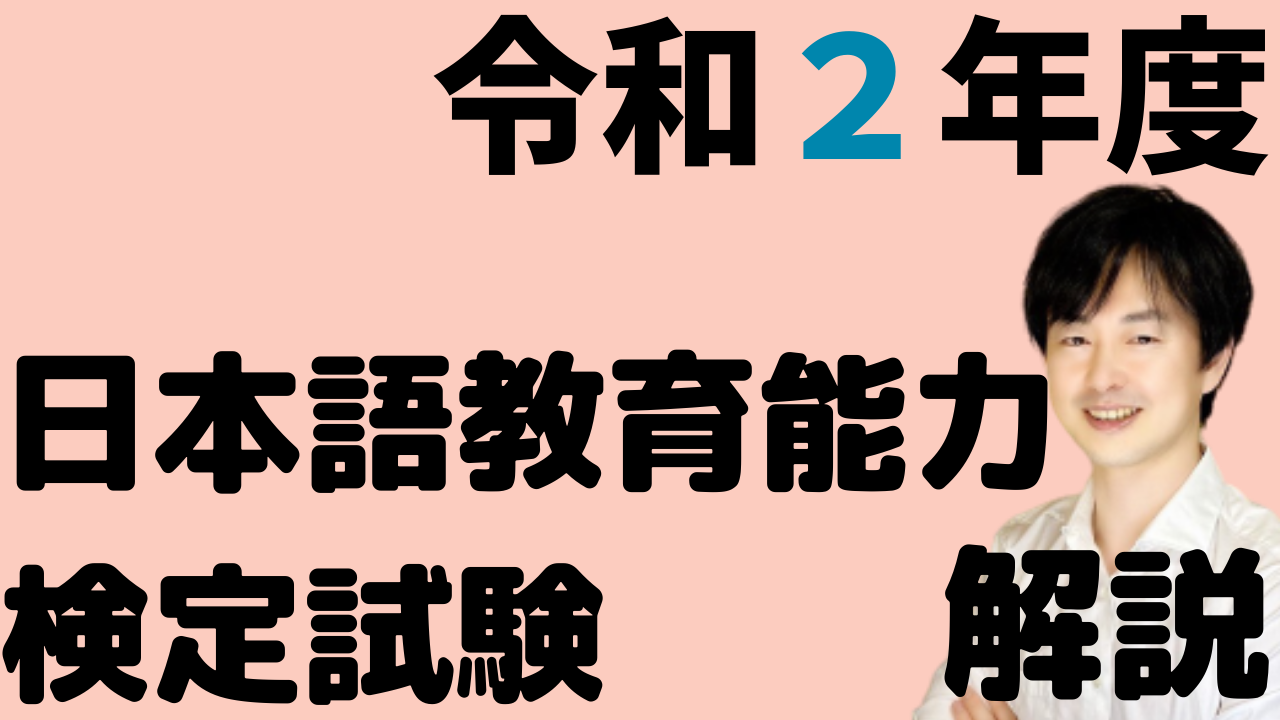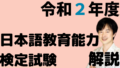令和2年度(2020年)日本語教育能力検定試験 試験Ⅱ(聴解・音声)問題6は例年通り、学習者が短い文を言うので、その中に含まれる誤りの説明として最も適当なものを選ぶ問題でした。
気を付けてください。私はここで集中力が切れてしまいました。
問題6は文が短く、次々と問題が飛んできます。
問題4と5で頭をフル回転されているので集中力が切れやすい。
これが最後なんだ!
問題の前に気合いを入れ直して、やりましょう。
問題6は聴解問題と言っていますが、実際は文法の知識を問う問題なので、聴解・音声が苦手な人でも対策をすれば、満点が狙えます。
各選択肢を見て、具体例がすぐ思い浮かぶようにしておきましょう。
試験Ⅱ問題6が最も大切な理由とは?
聴解問題6は文法の誤用問題
文法問題・誤用問題は試験Ⅱ以外でも多く出ます。
つまり試験Ⅱ問題6ができるようになれば他もできるようになるということ!
そこで問題集を用意しました。
完璧にして試験に向かいましょう。
問題6の解き方
①聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ。
②聞いて学習者の誤りを直す。
1番
聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ
転音とは?
転音とは、語が複合するときに、元の音が別の音に転ずること。
例)「雨(ame)」+「傘」→「雨傘(amagasa)」
音位転換とは?
音位転換とは、語の内部で子音が入れ替わる現象。読み方は「おんいてんかん」。発音しやすくするためなど。
例)「新しい」:あらたし→あたらし
「秋葉原」:あきばはら→あきはばら
「舌鼓」:したつづみ→したづつみ
「雰囲気(ふんいき)」を「ふいんき」と読んでしまったり、「とうもろこし」を「とうもころし」(となりのトトロのメイ)と読んでしまうのも音位転換のせい。
連濁とは?
連濁とは、2つの語が結合して、1語になるときに、後ろの語の最初の音が清音から濁音に変わること。
例)「雨」+「傘(かさ)」→「雨傘(あまがさ)」
連声とは?
連声とは、前の語の末尾の音[n][m][t]が、後ろの語のア行、ヤ行、ワ行に影響を与えて、タ行、ナ行、マ行の音に変わること。中世に起こったものが多い。なお、「れんじょう」と読みます。
例)「因縁」:いんえん→「いんねん」
聞いて学習者の誤りを直す
熱いフライパンに触って、手をやぶけしました。
→手をやけどしました。
やぶけ→やけど
音が全然違うので、どの選択肢も選べません…。
公式の答えを見ると、答えはbの音位転換
音位転換だとすると「やけど」→「やどけ」のはず。
ですが何度聞いても
「やどけ」ではなく「やぶけ」に聞こえます。
みなさんはどうですか?
この問題はできなくても気にしないでください。
答えはb
2番
聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ
a 副詞節の誤り
例)
例)たくさん勉強しても、試験に受かりました×
→たくさん勉強したので、試験に受かりました〇
b 接続助詞のあやまり
例)たくさん勉強しても、試験に受かりました×
→たくさん勉強したので、試験に受かりました〇
c 可能形の不使用
例)教えていただきませんか×
→教えていただけませんか〇
d 使役形の不使用
例)子供の頃はよく母にニンジンを食べられました。
→子供の頃はよく母にニンジンを食べさせられました。
聞いて学習者の誤りを直す
許してもらわなかった
→許してもらえなかった
「許してもらう」→可能形は「許してもらえる」
「許してもらわない」→可能形は「許してもらえない」
「許してもらわなかった」→可能形は「許してもらえなかった」
よって、答えはc
3番
聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ
a 副詞の誤り
例)あまり食べました×
→少し食べました〇
b 格助詞の誤り
例)ご飯が食べました×
→ご飯を食べました〇
c 条件表現の誤り
例)東京駅に着けば、乗り換えてください×(問題2(5)選択肢1より)
東京駅に着いたら、乗り換えてください〇
d 依頼を表す表現の誤り
例)教えていただきませんか×
→教えていただけませんか〇
聞いて誤りを直す
日本に行くと、ぜひ寿司を食べてください。
→日本に行ったら、ぜひ寿司を食べてください。
「と」「たら」は条件表現
よって、答えはc
4番
聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ
a 意向形の誤り
例)一緒に行きよう! 一緒に食ぼう!×
→一緒に行こう! 一緒に食べよう!〇
b 過去形の誤り
例)昨日、行きた×
→昨日、行った〇
c 命令形の誤り
例)行きろ! 食べ! ×
→行け! 食べろ! 〇
d 助動詞の活用形の誤り
例)彼は猫が好きにちがいないと思います。
→彼は猫が好きにちがいないだと思います。
聞いて誤りを直す
おみやげを食べろうとした
→おみやげを食べようとした
「食べよう」は意向形
よって、答えはa
5番
聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ
a 使役形の誤り
例)ニンジンを食べせた×
→ニンジンを食べさせた〇
b 助動詞の誤り(日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版のp42に助動詞の一覧あり)
例)猫が好きにべきだ×
→猫が好きに違いない〇
c 副詞の誤り
例)あまり食べました×
→少し食べました〇
d 助詞の誤り
例)ご飯が食べました×
→ご飯を食べました〇
聞いて誤りを直す
子どもたちがもっと外で遊ばせてあげたいです
→子どもたちにもっと外で遊ばせてあげたいです
「が」「に」は助詞です。
よって、答えはd
6番
聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ
a 名詞の誤り
例)地図を食べました×
→チーズを食べました〇
b 副詞の誤り
例)あまり食べました×
→少し食べました〇
c テンスの誤り
例)昨日猫カフェに行きます×
→昨日猫カフェに行きました〇
d 接続助詞のあやまり
例)たくさん勉強しても、試験に受かりました×
→たくさん勉強したので、試験に受かりました〇
聞いて誤りを直す
たいてい忘れました
→だいたい/ほとんど忘れました
「たいてい」:頻度を表す副詞
例)朝はたいてい勉強しています。
「だいたい/ほとんど」:1つの中の大部分を表す副詞
例)今日の勉強はだいたいわかりました。
よって、答えはb
7番
聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ
a 動詞の活用の誤り
例)読みた×
→読んだ〇
b 連体修飾の誤り
例)昨日プリン買ったがない×
→昨日買ったプリンがない〇
c 複合名詞の誤り
例)桜見が好きです×
→花見が好きです〇
d 形式名詞の誤り
例)私の夢は猫カフェを作るのです×
私の夢は猫カフェを作ることです〇
聞いて誤りを直す
買うのができます
→買うことができます
「の」「こと」は形式名詞
よって、答えはd
8番
聞く前に選択肢を見て誤りをイメージ
a 否定と肯定の混同
「あ、このバッグ、かわいくない?」「え、かわいくないと思いますか? 私はかわいいと思います」
b 格助詞と係助詞の混同
係助詞とは、助詞の一類。いろいろの語について、それらにある意味を添えて下の用言や活用連語にかかり、それらの用言や活用連語の述語としての働きに影響を及ぼすもの。口語では「は」「も」「こそ」「さえ」「でも」「しか」「だって」、文語では「は」「も」「ぞ」「なむ(なん)」「や」「か」「こそ」などがある(スーパー大辞林3.0より)
例)ご飯しか食べます×
→ご飯を食べます〇
c 疑問詞の付加の誤り
何が食べたいかどうかわかりません×
→何が食べたいか分かりません〇
d 複合助詞の誤り
例)勉強に対して話したいです×
→勉強について話したいです〇
聞いて誤りを直す
判断しかねません
→判断しかねます
「判断できない」と否定がしたくて「判断しかねません」と言っている。
否定と肯定の混同
よって、答えはa
各選択肢の例をもっと知りたい方へ
下の記事では過去10年分の選択肢を網羅しています。
下の記事に行き、
ウィンドウズパソコンは「Ctrl+F」
Macのパソコンは「command + F」
で検索窓が出ます。
そこに選択肢のキーワードを入力すれば、同じような選択肢が登場した過去問を調べることができます。