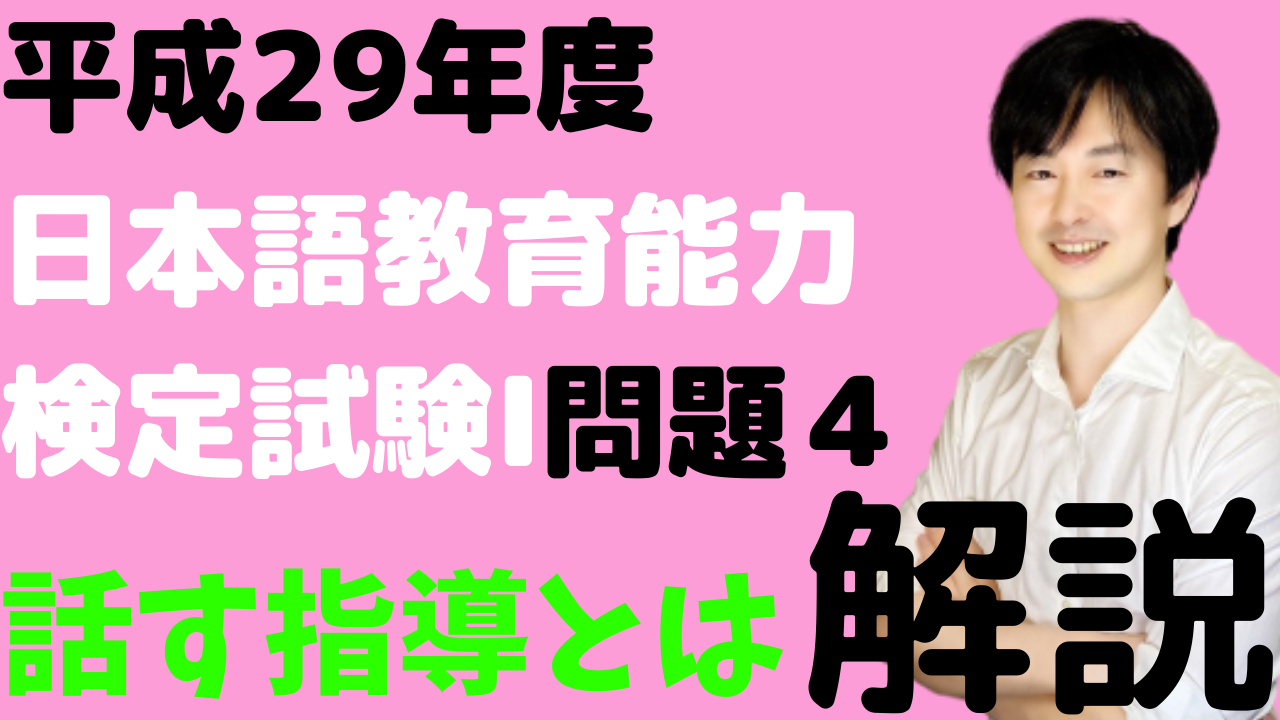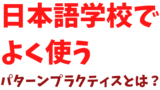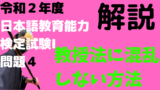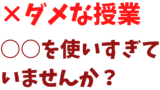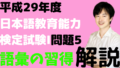H29(2017年度)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰの問題4の解説です。
平成29年度の問題4は【話すことの指導】に関する小問の集合になっていますが、これは珍しいです。
通常は問題3のように、まとまった文章を読んで問いに答えるパターンですから気を付けてください。
問題4では、教授法など、実際にどう指導するかといった問題が問われることが多いです。
問1の解き方
こういう問題は一瞬で解きたいです。
パターン・プラクティスと来ればオーディオ・リンガル・メソッド。
セットで理解してください。
よって、答えは3です。
パターン・プラクティスとは?
パターン・プラクティスは日本語教育能力検定試験の大好物ですから、確実に理解しておきましょう。
パターン・プラクティスとは、パターンの練習、型の練習、文型練習
基本的なパターンを繰り返し口頭で練習し、文法的に正確な発話をできるようにします。
詳しくは下の記事をどうぞ。
各選択肢の教授法も確認しておきましょう。
選択肢1
フォーカス・オン・フォームはこちら
選択肢2
コミュニカティブ・アプローチはこちら
選択肢3
オーディオ・リンガル・メソッドはこちら
選択肢4
TPRはこちら
その他の教授法:関連する過去問
教授法はほぼ毎年問われます!
最重要分野ですから、他の年度で問われた問題も一緒に確認して理解を深めましょう。
・令和2年度
・令和元年度
グアン・メソッドやナチュラル・アプローチなどの教授法
日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第4版の教授法の分野を確認した動画もあります。
問2の解き方
初級で用いる「モデル会話」はどんなものがいいんだろう?
想像力が要求される問題です。
モデル会話とは、教科書によく載っている会話例のことですね。
教科書のものをそのまま使うこともあれば、講師がモデル会話を考えなければならない場合もあります。
「初級」と書いてあることを見逃さずにチェックしてください。
各選択肢を見ていきます。
選択肢1 展開は不自然でよい?
不自然じゃダメです。
選択肢2 表現形式が複雑でもよい?
例えば、現実には敬語が使われたり、あいまいな言葉が使われたりしますが、初級ではダメですね。シンプルにしましょう。
× お休みの日は何をなさっていますか?
〇 休みの日は何をしていますか?
× 赤ペンを持ってたりしませんか?
〇 赤ペンを持っていますか?
選択肢3 個別性の強いものがよい?
個別性が強いとはそこでしか使えないということ。
例えば、
A:キラーマシンの心は、攻撃力が高いですか?
B:ええ、かなり高いですよ。
これは私がやっているドラクエウォークというゲームに関する会話ですが、このように個別性の強い会話を練習しても他では使えないのでもったいないですね。
初級ではなるべく、汎用性の高い言葉、色々な場面で使えそうな会話を練習したいです。
選択肢4 簡素化された自然なものがよい
会話の流れや設定は、簡素化された自然なものがいいですね。
よって、答えは4です。
関連する過去問
初級のモデル会話と言えば、令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5でも【初級のモデル会話を作成する際の留意点】を聞かれていますので要チェックです。
問3の解き方
「家族」「趣味」「教育」など項目が話題で分類されていますね。
これは話題(トピック)シラバスです。
よって、答えは3です。
シラバスの種類
日本語教育能力検定試験はシラバスが大好物で、毎年のように出題されます。
シラバスの種類や過去の出題例は下の記事にまとめましたので、よかったらどうぞ。
談話技能シラバスとは?
技能シラバスとは、「話す」「聞く」「読む」「書く」という4技能のいずれかに絞ったシラバス。
談話技能シラバスとは、話す技能を身に着けるためのシラバス。
話すために必要な技術ごとに項目が分類されていると思います。
場面シラバスとは?
場面シラバスとは、「市役所で」「レストランで」など場面ごとに分類されたシラバス。自分にとって必要な場面を選んで練習ができる。
話題シラバスとは?
話題シラバスとは、「家族について」「趣味について」「教育について」など話題(トピック)ごとに分類されたシラバス。話題ごとに語彙や表現を深めることができる。トピックシラバスとも。
機能シラバスとは?
機能シラバスとは、「謝罪する」「許可を求める」「依頼する」など機能ごとに分類されたシラバス。
問4の解き方
フィラーとは、会話の間に挟む言葉。それ自体に特段の意味はない。
選択肢を見ていきます。
選択肢1 へえー
「感心」を示しています。
選択肢2 えっと
特に意味がありません
選択肢3 わあ
「驚き」を示しています。
選択肢4 なるほど
「納得」を示しています。
よって、答えは2です。
フィラーは大切です
フィラーについての過去の出題例や日本語教育能力検定試験の予想問題、実際の授業で気を付けるべきことを記事にしましたので、よかったらどうぞ。
問5の解き方
これは知らないと難しい問題ですね。
深く考えたら正解が出せるという問題ではないので
分からなかったら適当に選んで、次に行きましょう。
日本語教育能力検定試験では、潔く諦める力も必要とされます。
話す力を評価するOPIとは?
OPIについてはこちら
各選択肢を見ていきましょう。
選択肢1
N5からN1の5段階はJLPT(日本語能力試験)です。
選択肢2
そのとおりです。相手のレベルに応じて質問を調整します。
選択肢3
学習者の自己評価は加味しません。録音したインタビューをテスト後に、テスターがもう一度聞きなおし、ガイドラインに照らして口頭運用能力(会話能力)を判定します。
選択肢4
言語知識ではなく、口頭運用能力(話す力)を判定します。
よって、答えは2です。
試験勉強を日本語教師の仕事につなげよう
問2は答えを出すのは簡単だったと思います。
知識としては、「これはいい」「これはだめ」とわかります。
ですが、実際にやるのは
そのとおりに初級のモデル会話を作ってみるのは
とても難しいです。
「初級のモデル会話を作るのはデリケートな作業なんだよ」
それを知ってほしくて、出題者は令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5でも似たような問題を出したのでしょう。
例えば、選択肢1の「不自然になってもよい」という件
初級の最初の方で【(場所)に○○があります】という文型を練習するのですが、例えば、シェアハウスのリビングで以下の場面はどうでしょう。
A:おはようございます。
B:おはようございます。
A:机の上にコップがあります。
B:そうですか。冷蔵庫の中にビールがあります。
A:へえ。バッグの中にビスケットがありますよ。
B:いいですね。
こんな不自然な展開の会話はだめですね。
例えば私だったら、
A:はあ。喉が渇きました。
B:Aさん、冷蔵庫にビールがありますよ。
A:ほんとですか!
というような会話にします。
その文型を使う必然性が、展開の自然さが求められます。
ですが、初級では使える文型、語彙が限られているので
実際にモデル会話を作ろうとすると大変です。
私は日本語教師1年目に初級のモデル会話作成でかなり苦しみました。